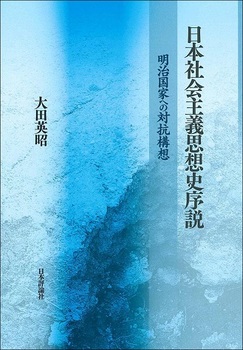メーデー その過去と現在、世界と日本 [日本・労働問題]
今日はメーデー。世界の労働者の祭典だ。世界各地で、実に多くの人びとがさまざまな趣向を凝らして街頭にくり出している様子は、ネットでも見ることができる。やはりこの日に国境を越えて同時に行うことに、メーデーの意義があることを強く感じる(日本の連合系メーデーが日をずらしているのは寂しい限り)。
中国ではメーデーを「五一国際労働節」という。習近平国家主席も昨日、視察先の新疆ウイグル自治区のウルムチで全国人民に向けてメーデーのあいさつを行い(その後ウルムチ南駅で爆発事件が発生)、新聞やテレビなどもメーデーのお祝いにあふれている(が、中国では民衆の集会や示威運動が厳しく制限されているため、これまた寂しい限り)。中国ではメーデーは三連休で旅行に出る人も多く、高速道路や鉄道は大混雑だ。
メーデーの起源は、アメリカで1886年5月1日に行われた8時間労働要求デモ(この直後にヘイマーケット弾圧事件が起きた)にある。国家権力の弾圧をはね返し労働者の権利を広げてゆくためには、労働者の国境を越えた連帯が不可欠であることから、1889年7月の第二インターナショナル創立大会で、毎年5月1日を国際的な闘争日とすることが決議された。翌1890年5月1日、第1回国際メーデーが開催され、欧米の各都市で多くの労働者が権利を求めてデモ行進を行った。
ちょうどその頃パリに滞在していた酒井雄三郎(中江兆民の弟子)は第1回メーデーにおける労働者の示威運動を取材し、欧米の労働運動や社会主義運動の現状や来歴について、日本の総合雑誌『国民之友』に詳しく書き送った(「五月一日の社会党運動会に就て」『国民之友』1890年7月23日)。日本でメーデーが知られるようになった端緒だ。こうした見聞を踏まえて酒井は、日本でも「トレードユニオン」(労働組合)をいずれ組織する必要があることを述べ、それを受けて『国民之友』社説も同様の主張をおこなった(「労働者の声」『国民之友』1890年9月23日)。それから7年後の1897年12月1日、金属・機械・造船業など重工業に従事する労働者1183名によって、日本最初の労働組合「鉄工組合」が結成される。
日本の第1回メーデーは1920年(ただし5月2日。翌年から5月1日)に開催されている。だが、日本で労働者が権利獲得を求めて最初に大規模な示威運動を行ったのは、その二十年前の1901年4月3日に開催された「労働者大懇親会」に遡る。この日、東京・向島の野外広場には、鉄工・活版工・人力車夫・魚河岸人足・木挽職・商店員など、さまざまな職種の労働者二万人以上が、職場・団体ごとに色とりどりの旗を押し立てて集結した。発起人の片山潜は満場の労働者を前に、労働法制・普通選挙権など労働者の権利を政府に要求する決議案を読み上げ、大拍手をもって採択された(拙著『日本社会民主主義の形成』日本評論社、2013年、第6章)。
それから百十数年、日本の労働者は長い苦難の運動を通じて、さまざまな権利をみずからの力で勝ち取ってきた。だがしばらく前から資本・経営側の反動攻勢が続き、安倍政権のもとで労働法制のさまざまな改悪が企まれている。先人たちの苦闘を無にしかねないような彼らの攻撃に対して、労働運動の側の足並みは乱れがちで、政権にへつらうような動きすらあるのは残念でならない。が、この〈冬の時代〉においても労働者の権利を守るために果敢に闘っている多くの人たちには敬意を表したい。
もちろん日本だけではない。アジア各国、欧米諸国でも、新自由主義グローバル経済のもとで資本側の攻勢が続く。国境を越えた労働運動の連携なしに、グローバル資本主義の攻勢をはね返すのは難しい。メーデーの原点に立ち戻って考えたい。
中国ではメーデーを「五一国際労働節」という。習近平国家主席も昨日、視察先の新疆ウイグル自治区のウルムチで全国人民に向けてメーデーのあいさつを行い(その後ウルムチ南駅で爆発事件が発生)、新聞やテレビなどもメーデーのお祝いにあふれている(が、中国では民衆の集会や示威運動が厳しく制限されているため、これまた寂しい限り)。中国ではメーデーは三連休で旅行に出る人も多く、高速道路や鉄道は大混雑だ。
メーデーの起源は、アメリカで1886年5月1日に行われた8時間労働要求デモ(この直後にヘイマーケット弾圧事件が起きた)にある。国家権力の弾圧をはね返し労働者の権利を広げてゆくためには、労働者の国境を越えた連帯が不可欠であることから、1889年7月の第二インターナショナル創立大会で、毎年5月1日を国際的な闘争日とすることが決議された。翌1890年5月1日、第1回国際メーデーが開催され、欧米の各都市で多くの労働者が権利を求めてデモ行進を行った。
ちょうどその頃パリに滞在していた酒井雄三郎(中江兆民の弟子)は第1回メーデーにおける労働者の示威運動を取材し、欧米の労働運動や社会主義運動の現状や来歴について、日本の総合雑誌『国民之友』に詳しく書き送った(「五月一日の社会党運動会に就て」『国民之友』1890年7月23日)。日本でメーデーが知られるようになった端緒だ。こうした見聞を踏まえて酒井は、日本でも「トレードユニオン」(労働組合)をいずれ組織する必要があることを述べ、それを受けて『国民之友』社説も同様の主張をおこなった(「労働者の声」『国民之友』1890年9月23日)。それから7年後の1897年12月1日、金属・機械・造船業など重工業に従事する労働者1183名によって、日本最初の労働組合「鉄工組合」が結成される。
日本の第1回メーデーは1920年(ただし5月2日。翌年から5月1日)に開催されている。だが、日本で労働者が権利獲得を求めて最初に大規模な示威運動を行ったのは、その二十年前の1901年4月3日に開催された「労働者大懇親会」に遡る。この日、東京・向島の野外広場には、鉄工・活版工・人力車夫・魚河岸人足・木挽職・商店員など、さまざまな職種の労働者二万人以上が、職場・団体ごとに色とりどりの旗を押し立てて集結した。発起人の片山潜は満場の労働者を前に、労働法制・普通選挙権など労働者の権利を政府に要求する決議案を読み上げ、大拍手をもって採択された(拙著『日本社会民主主義の形成』日本評論社、2013年、第6章)。
それから百十数年、日本の労働者は長い苦難の運動を通じて、さまざまな権利をみずからの力で勝ち取ってきた。だがしばらく前から資本・経営側の反動攻勢が続き、安倍政権のもとで労働法制のさまざまな改悪が企まれている。先人たちの苦闘を無にしかねないような彼らの攻撃に対して、労働運動の側の足並みは乱れがちで、政権にへつらうような動きすらあるのは残念でならない。が、この〈冬の時代〉においても労働者の権利を守るために果敢に闘っている多くの人たちには敬意を表したい。
もちろん日本だけではない。アジア各国、欧米諸国でも、新自由主義グローバル経済のもとで資本側の攻勢が続く。国境を越えた労働運動の連携なしに、グローバル資本主義の攻勢をはね返すのは難しい。メーデーの原点に立ち戻って考えたい。
2014-05-01 22:31
読書メモ:熊沢誠『労働組合運動とはなにか――絆のある働き方をもとめて』岩波書店、2013年1月 [日本・労働問題]

イギリス・アメリカの労働組合運動史から、21世紀日本の労働問題に至る、熊沢誠氏の数十年に及ぶ著作の数々を、私はこれまで愛読してきました。私が日本の労働・社会運動史の研究に手を染めるようになったのも、熊沢氏の『日本の労働者像(新編)』(1993年)と『民主主義は工場の門前で立ちすくむ(新編)』(1993年)から受けた衝撃と感動がきっかけでした。
労働運動史の名著『産業史における労働組合機能 』(1970年)や『国家のなかの国家』(1976年)はもちろん、現代日本の労働問題を扱った『能力主義と企業社会』(1997年)から『働きすぎに斃れて──過労死・過労自殺の語る労働史』(2010年)に至る熊沢氏の多くの著作を私は中国まで持参し、いつでもすぐ手にとれるように研究室の本棚に並べています。
熊沢氏の近著『労働組合運動とはなにか――絆のある働き方をもとめて』(岩波書店、2013年1月)は、それらのエッセンスを凝縮しつつ、現代日本の労働組合運動の再生の道を指し示した、渾身の力作です。労働問題に関心のある方はもちろん、新自由主義のはびこる日本社会の前途に不安をおぼえるすべての方々、とりわけ日々の生き残り競争にすり減らされ疲労を感じている方々に、ぜひ本書を一読することをおすすめします。老若男女の別を越えて、熊沢氏の訴えは読む者の胸に切実に響いてくるはずです。
熊沢氏の多くの著作に一貫する労働運動の思想は、本書中の次の文章に現れています。
「資本主義の公認の道徳は「競争せよ」です。市場競争のなかに自分を投げ込んで、そのなかで懸命に働いて稼ぎ、成功を求めよというもの。それに対抗する労働組合の思想とは、その公認の道徳に背を向ける、あるいは、少なくともそれは唯一の選択ではないと相対視して、なかま同士の競争を制限するものです。競争の成功を容易にする資源には、例えば「名門」の出身階層、大きな財産、並外れた知力や体力、芸術的またはスポーツ才能などがふくまれます。……そうした特別の競争資源に恵まれないふつうの人びと、一介の労働者としての「私」は、体制に唆〔そそのか〕される、成功の覚束ないサバイバル競争に投企して心身をすりへらすのではなく、運命がさして変わらないなかまとともに、自分たちの間での〈平等を通じての保障〉こそを追求したい――労働組合をつくり育てるものの考えはこのように表現していいでしょう。」(本書16ページ)
平たくいえば、ふつうの人びと(熊沢氏は「ノンエリート」とも言い換えます)がふつうに働き、ふつうに暮らしてゆけるようにすること。そしてそのために、ふつうの人びとが協力し助け合うこと。そこに労働組合の思想の本質を熊沢氏は見ているのです。このようにふつうの人びとがふつうに生きてゆけるというのは結局、社会の最も弱い立場に置かれた人びともまたふつうに生きられる、そんな社会をつくってゆくための基盤だと、私は思います。それに対して、あらゆる人びとが過酷な競争を強いられ、ふつうに生きてゆくのが難しい日本の(そして東アジアの)現代資本主義社会は、確かに病んでいます。
上のような観点から熊沢氏は、現代日本の労働運動の主流である企業別組合を厳しく批判しています。企業別組合のリーダーの多くは経営側の押しつける能力主義的な競争や選別を肯定しており、非正規労働者に対する差別的処遇を容認するのはもちろんのこと、過労死をはじめとするノンエリート社員の受難を救うことすらもできないというのです。
その一方で、熊沢氏は日本の企業別組合を頭から否定しているわけでもありません。企業別組合が戦後日本の企業社会に定着した歴史的背景を考えつつ、それが「産業別組合の職場支部」へと転換することで、非正規労働者との均等待遇や、能力主義的な競争・選別を制限する制度の要求に踏み出すことができると、熊沢氏は述べています。そのうえで、労働者の社会的な存在形態に応じて、コミュニティーユニオンなどいくつかのタイプの組合運動が発展することが、展望されています。ここに、現実の可視的な〈労働社会〉の中から育まれてゆく、ふつうの人びとの自生的な連帯の力を信じる熊沢氏の姿勢が、現れていると思います。
本書の出版に懸ける熊沢氏の熱い思いは、「あとがき」で次のように述べられています。「労働組合運動論が今の日本でいかに「一般受け」しないテーマであってもなお、労働組合というものの存在意義を、しんどい思いを抱えて働く人びとの心に沈殿させようとする「直球勝負」を試みたい」と。
昨年末の厚生労働省の発表によれば、日本の労働組合の推定組織率は、2013年6月末の時点で17.7%と、過去最低を記録しました。日本の労働組合運動はまさしく「冬の時代」にあるといえるでしょう。しかしこうした逆境にあるからこそ、熊沢氏とともに私も、日本のふつうの人々がふつうに暮らしてゆくために労働組合は決して欠かすことができないことを、声を大にして主張したいと思います。
日本と同じく、中国においても労働組合は「一般受け」しないテーマです。しかし、新自由主義的な競争の荒波に対する防波堤さらには抵抗の拠点として、労働組合運動は日本(そして東アジア)においてますます重要な意義を担うはずだと信じます。国境を越えた労働者のほんとうの連帯が実現する日を、夢見つつ。
2014-02-02 20:29