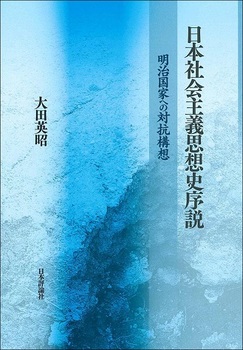「満洲国」の爪痕(6)――東本願寺新京別院旧跡 [満洲国]
長春第一の繁華街・重慶路。喧噪をよそに、路地に入って少し北に行くと、いかにも日本風の入母屋造の大屋根が目に入ってくる。旧・東本願寺新京別院の本堂だ。

この建物は、長春が「満洲国」の首都・新京と呼ばれていた1937年、真宗大谷派の満洲における布教拠点として竣工したが、満洲国滅亡・中華人民建国後は学校施設として使用されてきた。1985年に長春市の重要文化財に指定され、長春市第二実験中学の図書館・閲覧室として使われていたが、数年前に学校は移転し、建物の周囲で再開発が始まっている。
東本願寺(真宗大谷派)の中国大陸布教は1870年代に遡るが、その歩みは日清戦争後、日本国家の大陸への軍事的侵略に追随する形で進められた。日露戦争の結果、遼寧省南端の関東州(旅順・大連を含む)の租借権と長春・大連間の鉄道(後の南満洲鉄道=満鉄)権益をロシアから譲り受けると、日本仏教諸宗派は日本の勢力範囲に次々と拠点を置いて布教活動を行った。真宗大谷派も1919年、長春の満鉄附属地(日本が行政・軍事・警察・外交・司法権を行使)に布教拠点を設立している。
1931年9月18日、日本の関東軍の謀略で満洲事変が勃発すると、真宗大谷派(東本願寺)本山は早くもその翌日から軍への慰問行動を開始し、宗務総長は翌月、「国家の大方針を体認」し「国論の統一」に努めるよう諭達を発した。関東軍の武力によって満洲国が建国された1932年、日本政府の満洲移民政策に呼応する形で真宗大谷派は拓事講習所を開設し、開拓移民を精神面で支えることを目指した。
1934年には大谷光暢法主夫妻が満洲と華北を巡回し、満洲国皇帝溥儀に謁見、また満洲各地の布教所を視察して軍を慰問した。さらに同法主らは日中戦争勃発後の1938年1月から二か月にわたり、満洲各地および華北・華中における軍隊慰問のため、第二回の大陸巡教を行い、帰国後は日本全国で報告会が開催された。こうした大谷派の大陸巡教については、法主の妻(裏方)の大谷智子(裕仁〔昭和天皇〕の妻良子〔香淳皇后〕の妹)がその著作『光華抄』(実業之日本社、1940年)において、この「皇軍慰問の旅」の内容を詳しく述べ、「軍国の母を想ふ」「銃後婦人の覚悟」「戦歿勇士の遺族に」「長期建設の心構へ」などの小見出しで文を綴っている。
日本仏教の大陸布教は、1915年の「対華二十一か条の要求」の第五号において、中国での「日本人の布教権」を日本政府が要求したように、日本の軍事的大陸侵略と密接な関係がある。二十一か条要求の「布教権」は日本側が取り下げたので、中国における日本仏教の布教はしばらくの間、日本の植民地である関東州や満鉄附属地の居留日本人を主な対象としていた。が、満洲事変および満洲国成立後は、満洲国内の中国人への布教が積極的に試みられ、大谷派の満洲拓事講習所でも布教を目的とする中国語の学習が行われるようになった。
さらに日中戦争勃発後の1938年8月、文部省宗教局長は「支那布教に関する基本方針」の通牒を発し、「布教師をして住民の宣撫に当らしめ対支文化工作に寄与せしむること」が目的とされたことで、日本仏教の大陸布教は日本軍の特務機関の下請としての宣伝工作という意義を担うことになった。真宗大谷派は同年9月、東本願寺経営の「北京覚生女子中学校」を設立、また日本の傀儡となった汪兆銘〔精衛〕政権下の南京には「南京本願寺」や「金陵女子技芸学院」を設けるなど、日本軍特務機関との協力で戦時下の宣撫活動を積極的に担っていった。
こうした日本仏教の大陸布教は、独善的な日本仏教優位論に立って進められることも少なくなかった。例えば真宗大谷派のある布教使は、中国の仏教は「非常に低級」で「迷信が多く行はれてゐる」のに対して「日本に於ける仏教は、斯かる迷信を一掃した所の近代的人間生活に適応した高級な仏教」だと自画自賛している(「教育と宗教との提携(一)」『真宗』340号、1930年2月)。また日中戦争勃発後、大谷大学日曜学校研究会では、満洲事変に関する次のような教案素材が用いられることがあった。「あの満洲の大平野には、忠勇義烈なる陛下の赤子十万人が我が日本の生命線の礎となり、人柱となつて永久に埋れ居ます。…満洲大平野には、到る処に日の丸の旗が立てられ、土民達は情け深い日本軍のもとへ続々と集まつて来ました。…さうして事変が起つてから半年も経たぬ内に、新しく満洲国といふ国が誕生しました。…私たちは今すぐ銃を取つて戦場に立つことは出来ませんが、一心に勉強をし、銃後の護りは私達の手でしつかり握り合ひ、国家に対し御奉公申し上げる事を固く誓ひませう」(『真宗』457号、1939年9月)。
「貿易は国旗の後に付き従う」(trade follows the flag)というのが帝国主義の合言葉だとすれば、十五年戦争中の日本仏教の大陸布教はまさに、「仏法は国旗の後に付き従う」を実践したものだったと言えるだろう。日の丸に従属しながら満洲国全土に広まったように見えた日本仏教が、日本敗戦と満洲国崩壊後、あっという間に東北大平原から駆逐されたのも、必然の成り行きだった。東本願寺新京別院の旧跡は、かつて日本仏教が犯した罪業を今に伝えている。
なお敗戦後50年目の1995年、真宗大谷派の宗議会・参議会議員一同は、過去に宗門が犯した過ちを懺悔し、次の「不戦決議」を採択した。
私たちは過去において、大日本帝国の名の下に、世界の人々、とりわけアジア諸国の人たちに、言語に絶する惨禍をもたらし、佛法の名を借りて、将来ある青年たちを死地に赴かしめ、言いしれぬ苦難を強いたことを、深く懺悔するものであります。
この懺悔の思念を旨として、私たちは、人間のいのちを軽んじ、他を抹殺して愧じることのない、すべての戦闘行為を否定し、さらに賜った信心の智慧をもって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまないことを決意して、ここに 「不戦の誓い」を表明するものであります。
さらに私たちは、かつて安穏なる世を願い、四海同朋への慈しみを説いたために、非国民とされ、宗門からさえ見捨てられた人々に対し、心からなる許しを乞うとともに、今日世界各地において不戦平和への願いに促されて、その実現に身を捧げておられるあらゆる心ある人々に、深甚の敬意を表するものであります。
私たちは、民族・言語・文化・宗教の相違を越えて、戦争を許さない、豊かで平和な国際社会の建設にむけて、すべての人々と歩みをともにすることを誓うものであります。 右、決議いたします。
1995年6月13日
真宗大谷派 宗議会議員一同
1995年6月15日
真宗大谷派 参議会議員一同
また真宗大谷派東本願寺は、昨年開催された「第13回非戦・平和展」の際、宗務総長の署名で次のように述べている。
私たちの宗門は、明治期以降、宗祖親鸞聖人の仰せになきことを仰せとして語り、戦争に協力してきました。侵略戦争を「聖戦」と呼び、仏法の名のもとに、多くの青年たちを戦場へと送り出しました。そして遺族のみならず、アジア諸国、とりわけ中国、朝鮮半島の人々に、計り知れない苦痛と悲しみを強いてきました。さらに、非戦を願い、四海同朋への慈しみを説いたために、非国民とされた僧侶たちを見捨ててきました。
これらに対する懺悔の思念を旨として、宗門は1995年に「賜った信心の智慧をもって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまない」(「不戦決議」)という誓いを表明しました。
http://www.higashihonganji.or.jp/release_move/others/pdf/2013_peace_show.pdf
過去に犯した行為に対する真宗大谷派のこうした真摯な反省には、敬意を表したい。最近の安倍政権が目指す軍事大国化への傾向、例えば秘密保護法制定や集団的自衛権の行使容認への動きに対して、真宗大谷派が批判的見解を公式に表明しているのも、過去に日本帝国の戦争に協力した教団の歴史に対する反省に立つものといえる。
集団的自衛権の行使容認に反対する決議(真宗大谷派宗議会、2014年6月10日)
内閣総理大臣への「「特定秘密保護法案」の廃案に関する要望書」提出について(真宗大谷派宗務総長、2013年11月27日)
ところで中華人民共和国成立後、長らく学校施設として使われてきた旧東本願寺新京別院の建物は、長春市の重要文化財に指定されている。近年学校は移転し、付近では再開発が始まっているが、開発業者が無断でこの建物の一部を破壊していることが今年5月、新聞報道で伝えられた。近くに住む劉さんは次のように語る。「この建物は日本人が長春に建てたものですが、これは文化財です。一時期の歴史を代表するものです。なぜやすやすと壊してしまったのか」。長春市当局は開発業者に命じて工事を停止させ、現在調査中だという。
http://www.chinajilin.com.cn/jlnews/content/2014-05/07/content_3236486.htm
今月半ば、私は現場を訪れてみた。東本願寺新京別院の本堂の外観は前に掲げた写真のように無事に見えるが、屋根の一部や北側にある附属の建物が損壊されているようだ。敷地の外側の塀には、開発業者による宣伝の看板があり、東本願寺を高層ビルが取り囲む形で再開発の完成予想図が描かれている(写真下)。中国の現在を象徴しているかのようだ。

いつの日か、真宗大谷派の代表団がぜひこの遺跡を訪れ、過去に教団が犯した過ちを中国・長春の人びとに対して直接に懺悔することを、私は強く願っている。特に日本と中国との間に不穏な波風の立っている今こそ、良心ある日本の宗教者の真摯な行動が求められていると、私は思う。東アジアに平和の種を播くためにも。
(参考文献:江森一郎・孫伝釗「戦時下の東本願寺大陸布教とその教育事業の意味と実際」『金沢大学教育学部紀要 教育科学編』43号、1994年2月、木場明志「真宗大谷派による中国東北部(満洲)開教事業についての覚え書き」『大谷大学研究年報』42集、1991年2月、中濃教篤「仏教のアジア伝道と植民地主義」『講座日本近代と仏教6 戦時下の仏教』国書刊行会、1977年。)
この建物は、長春が「満洲国」の首都・新京と呼ばれていた1937年、真宗大谷派の満洲における布教拠点として竣工したが、満洲国滅亡・中華人民建国後は学校施設として使用されてきた。1985年に長春市の重要文化財に指定され、長春市第二実験中学の図書館・閲覧室として使われていたが、数年前に学校は移転し、建物の周囲で再開発が始まっている。
東本願寺(真宗大谷派)の中国大陸布教は1870年代に遡るが、その歩みは日清戦争後、日本国家の大陸への軍事的侵略に追随する形で進められた。日露戦争の結果、遼寧省南端の関東州(旅順・大連を含む)の租借権と長春・大連間の鉄道(後の南満洲鉄道=満鉄)権益をロシアから譲り受けると、日本仏教諸宗派は日本の勢力範囲に次々と拠点を置いて布教活動を行った。真宗大谷派も1919年、長春の満鉄附属地(日本が行政・軍事・警察・外交・司法権を行使)に布教拠点を設立している。
1931年9月18日、日本の関東軍の謀略で満洲事変が勃発すると、真宗大谷派(東本願寺)本山は早くもその翌日から軍への慰問行動を開始し、宗務総長は翌月、「国家の大方針を体認」し「国論の統一」に努めるよう諭達を発した。関東軍の武力によって満洲国が建国された1932年、日本政府の満洲移民政策に呼応する形で真宗大谷派は拓事講習所を開設し、開拓移民を精神面で支えることを目指した。
1934年には大谷光暢法主夫妻が満洲と華北を巡回し、満洲国皇帝溥儀に謁見、また満洲各地の布教所を視察して軍を慰問した。さらに同法主らは日中戦争勃発後の1938年1月から二か月にわたり、満洲各地および華北・華中における軍隊慰問のため、第二回の大陸巡教を行い、帰国後は日本全国で報告会が開催された。こうした大谷派の大陸巡教については、法主の妻(裏方)の大谷智子(裕仁〔昭和天皇〕の妻良子〔香淳皇后〕の妹)がその著作『光華抄』(実業之日本社、1940年)において、この「皇軍慰問の旅」の内容を詳しく述べ、「軍国の母を想ふ」「銃後婦人の覚悟」「戦歿勇士の遺族に」「長期建設の心構へ」などの小見出しで文を綴っている。
日本仏教の大陸布教は、1915年の「対華二十一か条の要求」の第五号において、中国での「日本人の布教権」を日本政府が要求したように、日本の軍事的大陸侵略と密接な関係がある。二十一か条要求の「布教権」は日本側が取り下げたので、中国における日本仏教の布教はしばらくの間、日本の植民地である関東州や満鉄附属地の居留日本人を主な対象としていた。が、満洲事変および満洲国成立後は、満洲国内の中国人への布教が積極的に試みられ、大谷派の満洲拓事講習所でも布教を目的とする中国語の学習が行われるようになった。
さらに日中戦争勃発後の1938年8月、文部省宗教局長は「支那布教に関する基本方針」の通牒を発し、「布教師をして住民の宣撫に当らしめ対支文化工作に寄与せしむること」が目的とされたことで、日本仏教の大陸布教は日本軍の特務機関の下請としての宣伝工作という意義を担うことになった。真宗大谷派は同年9月、東本願寺経営の「北京覚生女子中学校」を設立、また日本の傀儡となった汪兆銘〔精衛〕政権下の南京には「南京本願寺」や「金陵女子技芸学院」を設けるなど、日本軍特務機関との協力で戦時下の宣撫活動を積極的に担っていった。
こうした日本仏教の大陸布教は、独善的な日本仏教優位論に立って進められることも少なくなかった。例えば真宗大谷派のある布教使は、中国の仏教は「非常に低級」で「迷信が多く行はれてゐる」のに対して「日本に於ける仏教は、斯かる迷信を一掃した所の近代的人間生活に適応した高級な仏教」だと自画自賛している(「教育と宗教との提携(一)」『真宗』340号、1930年2月)。また日中戦争勃発後、大谷大学日曜学校研究会では、満洲事変に関する次のような教案素材が用いられることがあった。「あの満洲の大平野には、忠勇義烈なる陛下の赤子十万人が我が日本の生命線の礎となり、人柱となつて永久に埋れ居ます。…満洲大平野には、到る処に日の丸の旗が立てられ、土民達は情け深い日本軍のもとへ続々と集まつて来ました。…さうして事変が起つてから半年も経たぬ内に、新しく満洲国といふ国が誕生しました。…私たちは今すぐ銃を取つて戦場に立つことは出来ませんが、一心に勉強をし、銃後の護りは私達の手でしつかり握り合ひ、国家に対し御奉公申し上げる事を固く誓ひませう」(『真宗』457号、1939年9月)。
「貿易は国旗の後に付き従う」(trade follows the flag)というのが帝国主義の合言葉だとすれば、十五年戦争中の日本仏教の大陸布教はまさに、「仏法は国旗の後に付き従う」を実践したものだったと言えるだろう。日の丸に従属しながら満洲国全土に広まったように見えた日本仏教が、日本敗戦と満洲国崩壊後、あっという間に東北大平原から駆逐されたのも、必然の成り行きだった。東本願寺新京別院の旧跡は、かつて日本仏教が犯した罪業を今に伝えている。
なお敗戦後50年目の1995年、真宗大谷派の宗議会・参議会議員一同は、過去に宗門が犯した過ちを懺悔し、次の「不戦決議」を採択した。
私たちは過去において、大日本帝国の名の下に、世界の人々、とりわけアジア諸国の人たちに、言語に絶する惨禍をもたらし、佛法の名を借りて、将来ある青年たちを死地に赴かしめ、言いしれぬ苦難を強いたことを、深く懺悔するものであります。
この懺悔の思念を旨として、私たちは、人間のいのちを軽んじ、他を抹殺して愧じることのない、すべての戦闘行為を否定し、さらに賜った信心の智慧をもって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまないことを決意して、ここに 「不戦の誓い」を表明するものであります。
さらに私たちは、かつて安穏なる世を願い、四海同朋への慈しみを説いたために、非国民とされ、宗門からさえ見捨てられた人々に対し、心からなる許しを乞うとともに、今日世界各地において不戦平和への願いに促されて、その実現に身を捧げておられるあらゆる心ある人々に、深甚の敬意を表するものであります。
私たちは、民族・言語・文化・宗教の相違を越えて、戦争を許さない、豊かで平和な国際社会の建設にむけて、すべての人々と歩みをともにすることを誓うものであります。 右、決議いたします。
1995年6月13日
真宗大谷派 宗議会議員一同
1995年6月15日
真宗大谷派 参議会議員一同
また真宗大谷派東本願寺は、昨年開催された「第13回非戦・平和展」の際、宗務総長の署名で次のように述べている。
私たちの宗門は、明治期以降、宗祖親鸞聖人の仰せになきことを仰せとして語り、戦争に協力してきました。侵略戦争を「聖戦」と呼び、仏法の名のもとに、多くの青年たちを戦場へと送り出しました。そして遺族のみならず、アジア諸国、とりわけ中国、朝鮮半島の人々に、計り知れない苦痛と悲しみを強いてきました。さらに、非戦を願い、四海同朋への慈しみを説いたために、非国民とされた僧侶たちを見捨ててきました。
これらに対する懺悔の思念を旨として、宗門は1995年に「賜った信心の智慧をもって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまない」(「不戦決議」)という誓いを表明しました。
http://www.higashihonganji.or.jp/release_move/others/pdf/2013_peace_show.pdf
過去に犯した行為に対する真宗大谷派のこうした真摯な反省には、敬意を表したい。最近の安倍政権が目指す軍事大国化への傾向、例えば秘密保護法制定や集団的自衛権の行使容認への動きに対して、真宗大谷派が批判的見解を公式に表明しているのも、過去に日本帝国の戦争に協力した教団の歴史に対する反省に立つものといえる。
集団的自衛権の行使容認に反対する決議(真宗大谷派宗議会、2014年6月10日)
内閣総理大臣への「「特定秘密保護法案」の廃案に関する要望書」提出について(真宗大谷派宗務総長、2013年11月27日)
ところで中華人民共和国成立後、長らく学校施設として使われてきた旧東本願寺新京別院の建物は、長春市の重要文化財に指定されている。近年学校は移転し、付近では再開発が始まっているが、開発業者が無断でこの建物の一部を破壊していることが今年5月、新聞報道で伝えられた。近くに住む劉さんは次のように語る。「この建物は日本人が長春に建てたものですが、これは文化財です。一時期の歴史を代表するものです。なぜやすやすと壊してしまったのか」。長春市当局は開発業者に命じて工事を停止させ、現在調査中だという。
http://www.chinajilin.com.cn/jlnews/content/2014-05/07/content_3236486.htm
今月半ば、私は現場を訪れてみた。東本願寺新京別院の本堂の外観は前に掲げた写真のように無事に見えるが、屋根の一部や北側にある附属の建物が損壊されているようだ。敷地の外側の塀には、開発業者による宣伝の看板があり、東本願寺を高層ビルが取り囲む形で再開発の完成予想図が描かれている(写真下)。中国の現在を象徴しているかのようだ。
いつの日か、真宗大谷派の代表団がぜひこの遺跡を訪れ、過去に教団が犯した過ちを中国・長春の人びとに対して直接に懺悔することを、私は強く願っている。特に日本と中国との間に不穏な波風の立っている今こそ、良心ある日本の宗教者の真摯な行動が求められていると、私は思う。東アジアに平和の種を播くためにも。
(参考文献:江森一郎・孫伝釗「戦時下の東本願寺大陸布教とその教育事業の意味と実際」『金沢大学教育学部紀要 教育科学編』43号、1994年2月、木場明志「真宗大谷派による中国東北部(満洲)開教事業についての覚え書き」『大谷大学研究年報』42集、1991年2月、中濃教篤「仏教のアジア伝道と植民地主義」『講座日本近代と仏教6 戦時下の仏教』国書刊行会、1977年。)
タグ:満洲国
2014-06-25 21:08
「世界記憶遺産」の登録申請をめぐる日中対立 [日中関係]
中国外交部は6月10日、南京大虐殺や従軍慰安婦に関する国内資料を「世界記録遺産」としてユネスコに登録申請したことを発表した。それに対し、日本の菅義偉官房長官は11日午前の記者会見で、「中国がユネスコを政治的に利用し、日中間の過去の一時期における負の遺産をいたずらにプレーアップ(強調)していることは極めて遺憾だ」と批判して、中国政府に抗議し取り下げを求めたことを明らかにした。その際菅長官は、とくに南京大虐殺について「旧日本軍の南京入城後、殺害あるいは略奪行為があったことは否定できないが、具体的な(犠牲者の)数には様々な議論がある」と述べている。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140611-OYT1T50112.html
今回の悶着の背景には四か月前の出来事がある。今年2月、鹿児島県南九州市は知覧特攻平和会館が収蔵する特攻隊員の遺書や手紙について、世界記憶遺産登録の申請を行っていた(遺産登録の申請は政府だけでなく、非政府機関の団体・個人でも可能である)。それに対して中国外交部は2月10日、この登録申請は日本軍国主義の侵略の歴史を美化し、反ファシズム戦争の成果と戦後の国際秩序に挑戦するもので、ユネスコの趣旨に反しており、必ずや国際社会の強い非難と断固たる反対に遭うだろう、と批判した。
http://collection.sina.com.cn/yjjj/20140211/0930142454.shtml
四か月前の知覧の件は、批判内容の当否はともかく、中国政府が日本の一小自治体の行為を非難したものだ。なお世界記憶遺産の登録をめぐり、日本からは知覧特攻隊員の遺書のほか、「全国水平社」資料(奈良人権文化財団など)、「シベリア抑留者引揚」資料(京都府舞鶴市)、「東寺百合文書」(日本政府)、合わせて四件の申請があったが、ユネスコによる審議は一国につき二件までなので、日本の国内委員会は二件に絞り込まねばならない。
ところで今回の中国政府の南京大虐殺・従軍慰安婦資料の遺産登録申請に対する菅官房長官の批判は、知覧の件とは重みが異なる。日本政府が直接、中国政府の行為を批判し、申請の取り下げまでも要求しているのだ。
だが菅長官の批判する「ユネスコの政治利用」という言葉に、実質上の意味はあるのか?もしこんな批判が通用するなら、現在日本からユネスコに申請のある四件のうち、知覧の特攻隊員の遺書だけでなく、シベリア抑留者引揚資料についても「政治利用」と非難される恐れがあるのではないか?
中国政府は、特攻隊員の遺書の登録申請を「軍国主義の美化」「戦後国際秩序への挑戦」と、自己の歴史観の根本的立場から強烈に批判した。だが菅長官は?「政治利用」という曖昧な言葉を投げるほかは、「旧日本軍の南京入城後、殺害あるいは略奪行為があったことは否定できないが、具体的な(犠牲者の)数には様々な議論がある」などとケチをつけているに過ぎない。ここに、菅長官ら安倍政権の修正主義的歴史観の憫笑すべき弱さがある。
今、安倍政権は集団的自衛権の行使容認のための解釈改憲へ向けて、国民多数から批判を浴びれば浴びるほどますます前のめりに、突き進もうとしている。世界記憶遺産申請をめぐる彼らの中国批判も、どちらかと言えば内向きの理由、つまり右翼勢力から拍手喝采を受けて自派の引き締めを図るためのパフォーマンスのように映る。彼らの極右歴史観自体が内向きの語りに過ぎず、それが何かの拍子に外に飛び出して欧米諸国から批判を受けるたびに戦々兢々と弁明に追われるありさまは、滑稽としか言いようがない。
なお中国側の報道によれば、このたび遺産申請した南京大虐殺および慰安婦関係資料は、中央公文書館、中国第二歴史公文書館、遼寧省公文書館、吉林省公文書館、上海市公文書館、南京市公文書館、南京大虐殺紀念館の七機関の合同によるとのこと。
http://www.chinanews.com/gn/2014/06-11/6270246.shtml
うち吉林省公文書館の資料は、最近当ブログで紹介した関東憲兵隊の史料群が主体になっていると推測される。
長春で新たに公開された関東憲兵隊の史料群
関東憲兵隊の史料群(1)慰安婦関係史料1
上の記事でも書いたように、この史料の公刊は中国の国家的研究プロジェクトの一環として実施されており、史料選択の「政治」性(とくに最近の緊張する日中関係をめぐる)は否定できない。とはいえ、いずれも旧満洲国の首都新京(現・長春)に日本の関東憲兵隊が遺した一次資料で、よくぞ湮滅を免れて今日まで残ったものだと感動すら覚えさせるものだ。これらの資料は、中国側の「政治」的意図を超えて、人類全体が記憶すべき重要な遺産として、末永く保存されるべき価値をもっていることは間違いない。
本来なら、南京大虐殺や従軍慰安婦などの資料は、人類全体が永く悔恨の意をこめて記憶すべき共通の歴史遺産として、国境を越えて多くの市民や研究者が協力し調査・整理・保存に携わることが望ましい。とりわけ日本国は、かつて犯した罪業を真に反省し謝罪するためにも、そのような作業に自ら積極的に協力せねばならなかったはずだ。もしそうしていれば、東アジアの平和の礎を築く大きな力になっていたに違いない。が、日本国支配層の恥知らずな隠蔽と怠慢のために、これらの歴史遺産はむしろ国際的パワーゲームの具に変じてしまった。この悲しむべき事態が、戦後日本国家の怠慢によって生じたことを、日本国民は深く自覚せねばならないと思う。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140611-OYT1T50112.html
今回の悶着の背景には四か月前の出来事がある。今年2月、鹿児島県南九州市は知覧特攻平和会館が収蔵する特攻隊員の遺書や手紙について、世界記憶遺産登録の申請を行っていた(遺産登録の申請は政府だけでなく、非政府機関の団体・個人でも可能である)。それに対して中国外交部は2月10日、この登録申請は日本軍国主義の侵略の歴史を美化し、反ファシズム戦争の成果と戦後の国際秩序に挑戦するもので、ユネスコの趣旨に反しており、必ずや国際社会の強い非難と断固たる反対に遭うだろう、と批判した。
http://collection.sina.com.cn/yjjj/20140211/0930142454.shtml
四か月前の知覧の件は、批判内容の当否はともかく、中国政府が日本の一小自治体の行為を非難したものだ。なお世界記憶遺産の登録をめぐり、日本からは知覧特攻隊員の遺書のほか、「全国水平社」資料(奈良人権文化財団など)、「シベリア抑留者引揚」資料(京都府舞鶴市)、「東寺百合文書」(日本政府)、合わせて四件の申請があったが、ユネスコによる審議は一国につき二件までなので、日本の国内委員会は二件に絞り込まねばならない。
ところで今回の中国政府の南京大虐殺・従軍慰安婦資料の遺産登録申請に対する菅官房長官の批判は、知覧の件とは重みが異なる。日本政府が直接、中国政府の行為を批判し、申請の取り下げまでも要求しているのだ。
だが菅長官の批判する「ユネスコの政治利用」という言葉に、実質上の意味はあるのか?もしこんな批判が通用するなら、現在日本からユネスコに申請のある四件のうち、知覧の特攻隊員の遺書だけでなく、シベリア抑留者引揚資料についても「政治利用」と非難される恐れがあるのではないか?
中国政府は、特攻隊員の遺書の登録申請を「軍国主義の美化」「戦後国際秩序への挑戦」と、自己の歴史観の根本的立場から強烈に批判した。だが菅長官は?「政治利用」という曖昧な言葉を投げるほかは、「旧日本軍の南京入城後、殺害あるいは略奪行為があったことは否定できないが、具体的な(犠牲者の)数には様々な議論がある」などとケチをつけているに過ぎない。ここに、菅長官ら安倍政権の修正主義的歴史観の憫笑すべき弱さがある。
今、安倍政権は集団的自衛権の行使容認のための解釈改憲へ向けて、国民多数から批判を浴びれば浴びるほどますます前のめりに、突き進もうとしている。世界記憶遺産申請をめぐる彼らの中国批判も、どちらかと言えば内向きの理由、つまり右翼勢力から拍手喝采を受けて自派の引き締めを図るためのパフォーマンスのように映る。彼らの極右歴史観自体が内向きの語りに過ぎず、それが何かの拍子に外に飛び出して欧米諸国から批判を受けるたびに戦々兢々と弁明に追われるありさまは、滑稽としか言いようがない。
なお中国側の報道によれば、このたび遺産申請した南京大虐殺および慰安婦関係資料は、中央公文書館、中国第二歴史公文書館、遼寧省公文書館、吉林省公文書館、上海市公文書館、南京市公文書館、南京大虐殺紀念館の七機関の合同によるとのこと。
http://www.chinanews.com/gn/2014/06-11/6270246.shtml
うち吉林省公文書館の資料は、最近当ブログで紹介した関東憲兵隊の史料群が主体になっていると推測される。
長春で新たに公開された関東憲兵隊の史料群
関東憲兵隊の史料群(1)慰安婦関係史料1
上の記事でも書いたように、この史料の公刊は中国の国家的研究プロジェクトの一環として実施されており、史料選択の「政治」性(とくに最近の緊張する日中関係をめぐる)は否定できない。とはいえ、いずれも旧満洲国の首都新京(現・長春)に日本の関東憲兵隊が遺した一次資料で、よくぞ湮滅を免れて今日まで残ったものだと感動すら覚えさせるものだ。これらの資料は、中国側の「政治」的意図を超えて、人類全体が記憶すべき重要な遺産として、末永く保存されるべき価値をもっていることは間違いない。
本来なら、南京大虐殺や従軍慰安婦などの資料は、人類全体が永く悔恨の意をこめて記憶すべき共通の歴史遺産として、国境を越えて多くの市民や研究者が協力し調査・整理・保存に携わることが望ましい。とりわけ日本国は、かつて犯した罪業を真に反省し謝罪するためにも、そのような作業に自ら積極的に協力せねばならなかったはずだ。もしそうしていれば、東アジアの平和の礎を築く大きな力になっていたに違いない。が、日本国支配層の恥知らずな隠蔽と怠慢のために、これらの歴史遺産はむしろ国際的パワーゲームの具に変じてしまった。この悲しむべき事態が、戦後日本国家の怠慢によって生じたことを、日本国民は深く自覚せねばならないと思う。
2014-06-12 00:27
書評:鄭玹汀『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』 [日本・近代史]
鄭玹汀著『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館、2013年2月)に対する私の書評が、『初期社会主義研究』(25号、2014年5月)に掲載されました。下に転載します。
----------------------------------------
ここ数年来、日本社会のあちこちでナショナリズムの狂熱が噴出している。かつてインターネットの世界に閉じ込められていた民族差別な言辞が、突然現実の街路に飛び出し、日の丸や旭日旗を振り回す排外主義団体のデモの怒号となって東京の白昼の路上でもしばしば耳にするようになった。ここは本当に二十一世紀の日本なのか、と目を疑いたくなるような光景である。昨年(二〇一二年)末の安倍晋三政権の発足以来、排外的国家主義の圧力が公共の場の言論に対しても強まっているのは確かだ。領土問題でやや踏み込んだ発言を行った元首相に対しては、現職の閣僚から「国賊」という言葉が投げつけられた。あたかも時計の針が「戦前」へと逆戻りしたかのようである。
日本社会全体に強まりつつある国家主義の圧力は、権力を批判する側の人びとの立ち位置すら微妙に変化させているようにみえる。例えば反原発・反TPPを掲げる運動や言論においても、普遍的な人権を根拠として立論するよりもむしろ、「国民国家」を守るためといったナショナルな立場からの主張が目立ってきている。「反日」「左翼」というレッテルを張られることを恐れる空気が強まるなかで、「保守」「愛国者」を自称する論客が若い世代に増えている。日本近代思想史研究の分野で近年、保守思想に関心が集まっていることも、そうした空気の反映なのかもしれない。
日本社会の右傾化が目立つ中、二〇一三年二月に刊行された鄭玹汀氏の『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館)は、反時代的であるがゆえにタイムリーな意義をもっている。本書の主人公である木下尚江は、私見によれば、近代日本においてナショナリズムと国体論に対する最もラディカルな批判を敢行した思想家の一人である。本書は、清水靖久氏の『野生の信徒 木下尚江』(九州大学出版会、二〇〇二年)以来約十年ぶりに現れた木下に関する本格的な研究書であり、木下の真骨頂である国家主義批判の思想と正面から取り組みつつ、彼を中心に明治キリスト教界のあり方全体を視野に収めた労作といえる。
本書が研究対象とする時代は、一八八〇年代後半から一九一〇年頃に至る二十数年間である。大日本帝国憲法および教育勅語の発布から日清・日露の両戦争を経て大逆事件に至るこの時期、明治政府は天皇制イデオロギーによる急速な国民統合の実現を目指していた。そうした動きに、キリスト教界がどのように対峙ないし屈服していったかを考察することに、本書の主眼が置かれている。植村正久・海老名弾正・巌本善治ら明治キリスト教界を代表する指導者たちは、キリスト教への圧迫が強まるこの時期、天皇制イデオローグの呼号する国家主義や家族主義への妥協を重ねていった。他方で木下ら少数のキリスト者たちは、そうした教界主流の姿勢を厳しく批判したのである。従来注目されてこなかったこの両者の思想的対決を、鄭氏はスリリングな筆致でえぐりだしている。
本書の議論で最も興味深く思われるのは、「武士道」思想をめぐる両者の対立である。植村正久ら明治期の代表的キリスト者の多くが武士道を称揚したのは周知のことだが、従来の研究はこれをキリスト教の土着化として積極的に捉えるものがほとんどであった。そうした先行研究に対し、鄭氏は異を唱える。植村らによる武士道の宣揚は、キリスト教を反国家的だとするナショナリスト勢力の攻撃から身をかわし、キリスト教が愛国や国粋保存と調和することを示すためという側面があった。日清・日露戦争にキリスト教界が積極的に加担する論理としても武士道は用いられた。木下の武士道批判はキリスト教界主流のこうした姿勢を指弾するもので、日露戦争を是認するか否かをめぐって両者の対立は頂点に達することが、本書で詳しく論じられている。世界に誇る日本の伝統的な倫理思想として武士道をもてはやす声が近年とみに高まっているが、そうした風潮の危うさに警鐘を鳴らすものとして、木下の武士道批判が掘り起こされたことの意義は小さくない。
さらに、明治キリスト教界の女性論をめぐる本書の研究も、たいへん刺激的である。教界主流の女性論の保守化、内村鑑三ら男性中心主義的なキリスト者と日本基督教婦人矯風会との対立、矯風会内部の保守派と進歩派との対立など、時代の変遷とともに変化する複雑な構図が丁寧に解きほぐされている。そして女性の社会的役割をめぐるこうした教界内の論争が、天皇制イデオロギーの支柱の一つである家族主義の受容についての葛藤を反映していたこと、したがってそこには天皇制国家体制へのキリスト教界の統合という問題も蔵されていたことが、解明されている。鄭氏によれば、当時もっとも進歩的でラディカルな女性観をもっていたキリスト者の一人が木下であった。彼は廃娼運動を通じて矯風会の進歩派の女性クリスチャンと交流を深め、最も弱い立場に置かれた娼妓を主体とする人権運動の構想へと、女性解放の思想を深めていった。木下が婦人参政権をいち早く主張し、その獲得のための運動を矯風会の女性たちに呼びかけていた事実を、鄭氏が新資料の発掘によって明らかにしたことは、日本政治思想史研究のうえでも貴重な成果といえよう。
木下尚江研究の重要なテーマの一つとして、一九〇六年秋以降の彼における思想上の変化をどのように捉えるか、という問題がある。従来の研究では、木下は母親の死などをきっかけに政治運動・社会運動から撤退し、キリスト教信仰にも動揺をきたして修養運動に参加するなど、急速に内面化してゆく、という理解が一般的といえよう。だが鄭氏はこうした見方にも疑問を呈している。すなわち木下の思想変化の基本線は、従来の都市知識人中心の運動を農村民衆中心の運動へと止揚することを目指す、という運動観の転回にあり、谷中村残留民との関わりの中にこの方向が示唆されているという。それと並行して、女性観においては都市の中・上流婦人からなる矯風会に対する木下の期待が失われた一方、農山村の最底辺の女性たちに変革への希望が託されるようになった。その間、彼の国家権力批判はますます熾烈となり、その背景として彼のキリスト教信仰における「神の国」観が深化したことが指摘されている。木下の思想変化の本質をめぐる本書のこうした叙述はまだスケッチにとどまっているが、従来の研究を刷新すべき重要な指摘が含まれていると思う。今後さらにこの問題をめぐる考察が深まることを期待したい。
本書を通読して見えてくることは、廃娼運動・社会主義運動・反戦運動など、木下の参加したあらゆる運動における彼の主張の根底に、天皇制批判の思想が脈々と流れていることである。明治日本の思想家のなかで、天皇制・国体論批判の深度において木下の右に出る者はいないだろう。近代日本の社会・政治運動において、天皇制問題が現在に至るまでしばしば躓きの石となってきたことを振り返るとき、彼の天皇制批判は燦然と光を放っている。天皇元首化に向けた憲法改正を右派支配層が推し進めようとしている現在、権力を監視し批判する側の人びとの間ですら、天皇制を儀礼的な君主制の一形態として肯定、むしろ賛美する言説がじわじわと広がっている。近代日本のキリスト教界は天皇制イデオロギーといったん妥協して以後、帝国日本の侵略戦争に協力する方向へずるずると引き込まれていった。それは決してキリスト教界だけの問題ではないし、また過去の問題でもない。東アジアにさまざまな不幸をもたらした日本ナショナリズムにおいて、天皇制はいかなる役割を果たしてきたのか、また現に果たしつつあるのか。私たちはそのことをもう一度熟考する必要があるし、今日木下尚江を読み直す最大の意義もそこにある。そのために本書は最も適切な案内役となるだろう。

----------------------------------------
ここ数年来、日本社会のあちこちでナショナリズムの狂熱が噴出している。かつてインターネットの世界に閉じ込められていた民族差別な言辞が、突然現実の街路に飛び出し、日の丸や旭日旗を振り回す排外主義団体のデモの怒号となって東京の白昼の路上でもしばしば耳にするようになった。ここは本当に二十一世紀の日本なのか、と目を疑いたくなるような光景である。昨年(二〇一二年)末の安倍晋三政権の発足以来、排外的国家主義の圧力が公共の場の言論に対しても強まっているのは確かだ。領土問題でやや踏み込んだ発言を行った元首相に対しては、現職の閣僚から「国賊」という言葉が投げつけられた。あたかも時計の針が「戦前」へと逆戻りしたかのようである。
日本社会全体に強まりつつある国家主義の圧力は、権力を批判する側の人びとの立ち位置すら微妙に変化させているようにみえる。例えば反原発・反TPPを掲げる運動や言論においても、普遍的な人権を根拠として立論するよりもむしろ、「国民国家」を守るためといったナショナルな立場からの主張が目立ってきている。「反日」「左翼」というレッテルを張られることを恐れる空気が強まるなかで、「保守」「愛国者」を自称する論客が若い世代に増えている。日本近代思想史研究の分野で近年、保守思想に関心が集まっていることも、そうした空気の反映なのかもしれない。
日本社会の右傾化が目立つ中、二〇一三年二月に刊行された鄭玹汀氏の『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館)は、反時代的であるがゆえにタイムリーな意義をもっている。本書の主人公である木下尚江は、私見によれば、近代日本においてナショナリズムと国体論に対する最もラディカルな批判を敢行した思想家の一人である。本書は、清水靖久氏の『野生の信徒 木下尚江』(九州大学出版会、二〇〇二年)以来約十年ぶりに現れた木下に関する本格的な研究書であり、木下の真骨頂である国家主義批判の思想と正面から取り組みつつ、彼を中心に明治キリスト教界のあり方全体を視野に収めた労作といえる。
本書が研究対象とする時代は、一八八〇年代後半から一九一〇年頃に至る二十数年間である。大日本帝国憲法および教育勅語の発布から日清・日露の両戦争を経て大逆事件に至るこの時期、明治政府は天皇制イデオロギーによる急速な国民統合の実現を目指していた。そうした動きに、キリスト教界がどのように対峙ないし屈服していったかを考察することに、本書の主眼が置かれている。植村正久・海老名弾正・巌本善治ら明治キリスト教界を代表する指導者たちは、キリスト教への圧迫が強まるこの時期、天皇制イデオローグの呼号する国家主義や家族主義への妥協を重ねていった。他方で木下ら少数のキリスト者たちは、そうした教界主流の姿勢を厳しく批判したのである。従来注目されてこなかったこの両者の思想的対決を、鄭氏はスリリングな筆致でえぐりだしている。
本書の議論で最も興味深く思われるのは、「武士道」思想をめぐる両者の対立である。植村正久ら明治期の代表的キリスト者の多くが武士道を称揚したのは周知のことだが、従来の研究はこれをキリスト教の土着化として積極的に捉えるものがほとんどであった。そうした先行研究に対し、鄭氏は異を唱える。植村らによる武士道の宣揚は、キリスト教を反国家的だとするナショナリスト勢力の攻撃から身をかわし、キリスト教が愛国や国粋保存と調和することを示すためという側面があった。日清・日露戦争にキリスト教界が積極的に加担する論理としても武士道は用いられた。木下の武士道批判はキリスト教界主流のこうした姿勢を指弾するもので、日露戦争を是認するか否かをめぐって両者の対立は頂点に達することが、本書で詳しく論じられている。世界に誇る日本の伝統的な倫理思想として武士道をもてはやす声が近年とみに高まっているが、そうした風潮の危うさに警鐘を鳴らすものとして、木下の武士道批判が掘り起こされたことの意義は小さくない。
さらに、明治キリスト教界の女性論をめぐる本書の研究も、たいへん刺激的である。教界主流の女性論の保守化、内村鑑三ら男性中心主義的なキリスト者と日本基督教婦人矯風会との対立、矯風会内部の保守派と進歩派との対立など、時代の変遷とともに変化する複雑な構図が丁寧に解きほぐされている。そして女性の社会的役割をめぐるこうした教界内の論争が、天皇制イデオロギーの支柱の一つである家族主義の受容についての葛藤を反映していたこと、したがってそこには天皇制国家体制へのキリスト教界の統合という問題も蔵されていたことが、解明されている。鄭氏によれば、当時もっとも進歩的でラディカルな女性観をもっていたキリスト者の一人が木下であった。彼は廃娼運動を通じて矯風会の進歩派の女性クリスチャンと交流を深め、最も弱い立場に置かれた娼妓を主体とする人権運動の構想へと、女性解放の思想を深めていった。木下が婦人参政権をいち早く主張し、その獲得のための運動を矯風会の女性たちに呼びかけていた事実を、鄭氏が新資料の発掘によって明らかにしたことは、日本政治思想史研究のうえでも貴重な成果といえよう。
木下尚江研究の重要なテーマの一つとして、一九〇六年秋以降の彼における思想上の変化をどのように捉えるか、という問題がある。従来の研究では、木下は母親の死などをきっかけに政治運動・社会運動から撤退し、キリスト教信仰にも動揺をきたして修養運動に参加するなど、急速に内面化してゆく、という理解が一般的といえよう。だが鄭氏はこうした見方にも疑問を呈している。すなわち木下の思想変化の基本線は、従来の都市知識人中心の運動を農村民衆中心の運動へと止揚することを目指す、という運動観の転回にあり、谷中村残留民との関わりの中にこの方向が示唆されているという。それと並行して、女性観においては都市の中・上流婦人からなる矯風会に対する木下の期待が失われた一方、農山村の最底辺の女性たちに変革への希望が託されるようになった。その間、彼の国家権力批判はますます熾烈となり、その背景として彼のキリスト教信仰における「神の国」観が深化したことが指摘されている。木下の思想変化の本質をめぐる本書のこうした叙述はまだスケッチにとどまっているが、従来の研究を刷新すべき重要な指摘が含まれていると思う。今後さらにこの問題をめぐる考察が深まることを期待したい。
本書を通読して見えてくることは、廃娼運動・社会主義運動・反戦運動など、木下の参加したあらゆる運動における彼の主張の根底に、天皇制批判の思想が脈々と流れていることである。明治日本の思想家のなかで、天皇制・国体論批判の深度において木下の右に出る者はいないだろう。近代日本の社会・政治運動において、天皇制問題が現在に至るまでしばしば躓きの石となってきたことを振り返るとき、彼の天皇制批判は燦然と光を放っている。天皇元首化に向けた憲法改正を右派支配層が推し進めようとしている現在、権力を監視し批判する側の人びとの間ですら、天皇制を儀礼的な君主制の一形態として肯定、むしろ賛美する言説がじわじわと広がっている。近代日本のキリスト教界は天皇制イデオロギーといったん妥協して以後、帝国日本の侵略戦争に協力する方向へずるずると引き込まれていった。それは決してキリスト教界だけの問題ではないし、また過去の問題でもない。東アジアにさまざまな不幸をもたらした日本ナショナリズムにおいて、天皇制はいかなる役割を果たしてきたのか、また現に果たしつつあるのか。私たちはそのことをもう一度熟考する必要があるし、今日木下尚江を読み直す最大の意義もそこにある。そのために本書は最も適切な案内役となるだろう。

2014-06-07 17:41