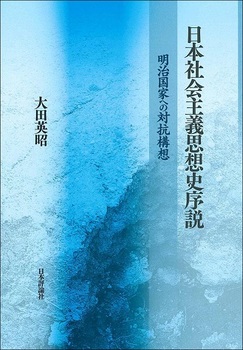岡崎一氏の拙著への書評(『初期社会主義研究』30号)に対する応答 [日本・近代史]
拙著『日本社会主義思想史序説―明治国家への対抗構想』(日本評論社、2021年)について、岡崎一氏(元東京都立大学教授)による書評が『初期社会主義研究』(30号、2022年3月)に掲載された、との知らせを受けた。
私は中国にいるので、当該号はしばらく入手できない。が、幸い同誌編集部の方が最終校正刷りのPDFファイルを送ってくださったので、書評を閲読することができた。
拙著を「初期社会主義研究に果敢に挑戦する刺激的好著」とする岡崎氏の評言はありがたく、当該分野における氏の長年の研究に基づく有益な指摘は尊重したい。ただし、氏の見解の中には、首をひねらざるを得ないもの、研究者としてとうてい承服できないものも少なくない。以下、岡崎氏の書評のうち疑問を感じる個所について、私からの応答を記しておきたい(なお『初期社会主義研究』30号の引用ページ数は最終校正刷りによる)。
私は拙著の序章4頁で、城多虎雄「論欧洲社会党」(『朝野新聞』1882年6~8月)について、「この論説は、「社会党ノ主義」=社会主義の理論と運動について、日本で初めて体系的に紹介したものといってよい」と記した。こうした私の評価について、岡崎氏は次のように批判している。
(『初期社会主義研究』30号、260~261頁)
岡崎氏は、私があたかも『明治文化資料叢書』第5巻社会主義編を見落としたかのように推測しているが、理解に苦しむ。私はこの巻を持っているし、目を通してもいる。そもそも久松の『理想境事情』は、昔は稀覯本だったかもしれないが、今では国会図書館デジタルコレクションに収録されており、誰でも容易に閲読できる。確かに数十年前なら『明治文化全集』などの史料集に頼らざるを得ない研究状況があったのだろうが、史料へのアクセスが格段に向上している現在はそうではない。
久松の『理想境事情』と、城多の長大な論文「論欧洲社会党」との内容を比較すれば、両者の水準の差は明らかである。久松の『理想境事情』は、社会主義を単純に国民同権や財産平等分配の主張と同一視したうえで、ヨーロッパの社会主義者や運動を羅列的に紹介しているに過ぎない。対して城多の「論欧洲社会党」は、中等社会(ブルジョアジー)と労力社会(プロレタリアート)との対立から「近世文明」における社会主義発生の必然性を論じ、第一インターナショナルおよびドイツ・ロシア・フランス・イギリスの社会主義運動の発展過程をそれぞれ詳しく紹介したうえで、生産手段の共有と公平な分配という根本的主張に至る社会主義の論理を考察し、その主張の是非について独自の検討を加えている。
このように、社会主義の理論と運動史の体系的な把握において、城多の重厚な論考は久松の編著の薄っぺらな内容を圧倒しているのである。私が城多の論説を「社会主義の理論と運動について、日本で初めて体系的に紹介したもの」であると考える根拠はここにある。
なお、単に社会主義の理論と運動を紹介するだけであれば、久松の『理想境事情』よりはるか前の1878~79年に、『東京日日新聞』を始めとする在京の諸新聞がそれを活発に行っていたことは、拙著の第一章で詳論したとおりである。
また、拙著の序章で、1890年代初頭に特徴的な社会主義理解の例として、陸羯南と内藤湖南とを挙げたことについて、岡崎氏は次のように批判している。
(『初期社会主義研究』30号、261頁)
長澤別天の社会主義論については、私は前著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の第4章第1節で扱っているので、参照されたい。私がこのたび拙著の序章「近現代日本における「社会主義」概念の展開」を書くにあたっては、長澤よりも早い時期に書かれた陸・内藤の社会主義観の方にこそ、当時の「国民主義」・「国粋保存主義」に基づく独特な見解が色濃く現れていると考えてこれを紹介した一方、長澤の社会主義論は紙幅の関係上割愛したのである。
次に拙著第1章での、1878年12月の『横浜毎日新聞』における「社会党」論に関して、岡崎氏は次のように指摘している。
(『初期社会主義研究』30号、261頁)
島田三郎は、日本最初の日刊紙として明治三年十二月(1871年1月)に創刊された『横浜毎日新聞』の草創期である73年に入社し、翌年社員総代の島田豊寛の養子となった。ただし島田三郎は75年元老院に入って(のち文部省に移る)、いったん同紙から離れており、明治十四年の政変(81年10月)で免官された後、『東京横浜毎日新聞』に再入社している。したがって、1878年12月の『横浜毎日新聞』社説の内容が、「島田三郎の存在抜きには考えられ」ないという岡崎氏の断言は、根拠が疑わしく、首肯できない。
同じく拙著第1章で言及した『郵便報知新聞』の「社会党」論に関し、岡崎氏は次のように指摘する。
(『初期社会主義研究』30号、261頁)
矢野龍渓は『郵便報知新聞』紙上で、「貧民救助法ヲ論ズ」(1876年6月8日)など社会問題に関係する社説を早い時期から書いており、後年の社会主義への関心とあわせて考えると、岡崎氏の指摘どおり確かに興味深いといえる。ただし、私は前著『日本社会民主主義の形成』第9章第2節および第4節で、1902年春から片山潜と矢野との交流が始まり、同年7月から矢野が社会主義協会の演説会に出演するようになったことや、片山の主宰する『労働世界』に「社会主義談」「四級団改善の急務」など矢野の談話・論説が掲載された事実を指摘し、また矢野のユートピア小説『新社会』を、それに対する木下尚江の批評とあわせて紹介している。したがって、「著者の視角には入ってはいない」などとする岡崎氏の決めつけはいただけない。
(『初期社会主義研究』30号、261~262頁)
第4章での研究対象は、初期民友社の社会・労働問題論として1887年から1890年の時期に限定している。したがって、北村透谷の1894年の評論や、内田魯庵の小説「くれの廿八日」(1898年)は、本稿での比較検討の対象外である。
(『初期社会主義研究』30号、262頁)
これは誤記でも誤植でもなく、『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという事実に基づく正しい表記である。労働組合期成会について最も詳細な研究をしてきた二村一夫氏も、次のように指摘している。「1897(明治30)年12月1日、労働組合期成会の機関紙『労働世界』が創刊されました。もともと機関紙の刊行は創立当初から計画され…」、「『労働世界』は、復刻版がサイズを縮小して刊行されたことなどから、しばしば「雑誌」と間違えられていますが、実際はタブロイド判の新聞でした」(「高野房太郎とその時代 (71)」『二村一夫著作集』(オンライン版))。
事実、当時の『労働世界』は当事者たちによって例外なく「新聞」と称されているのである(「鉄工組合本部臨時本部委員総会議事速記録」『労働世界』55号、1900年2月15日、附録第一~二面)。
片山潜が主筆を務めた『労働世界』は、第一次と第二次とに区別される。第一次『労働世界』は、労働組合期成会(および鉄工組合)の機関紙として1897年12月から1901年12月まで全100号が発行された、新聞体の定期刊行物である。他方、第二次『労働世界』は、1902年4月から1903年3月『社会主義』に改題されるまで発行された、雑誌体の定期刊行物である。岡崎氏はおそらく両者を混同しているのではあるまいか。
なお、当時の「新聞紙条例」には新聞と雑誌の明確な概念的区別はなく(どちらも新聞紙条例により取り締まりを受けた)、両者は主に体裁によって区別されていたといってよい(ただし雑誌のうち、「専ラ学術、技芸、統計、広告ノ類ヲ記載スル雑誌」については「新聞紙条例」ではなく「出版法」の規制を受けた)。
そして、岡崎氏の次のような私への〈アドバイス〉には看過できない問題がある。
(『初期社会主義研究』30号、263頁)
ここには、現在差別語として他者の尊厳を傷つける恐れのある歴史的語彙の扱いについての、岡崎氏と私との間に横たわる認識の落差がある。現在中国で歴史教育に携わっている私は、「支那」という語がその歴史的経緯のために、いかに中国の人びとの尊厳を傷つける言葉であるかを、痛切に理解している。だから、歴史的史料からの引用においても、当時の文脈におけるこの語の使われ方はどうであれ、この語が現在注記なしには決して用いられるべきではないことを示すために、繁雑をいとわずあえてこの語に〔ママ〕と傍記した次第である。この件について岡崎氏の考え方は私と異なるらしいが、氏の〈アドバイス〉を受け容れることはできない。
以上、拙著に対する岡崎氏の書評のうち、疑問を感じる箇所について私からの応答を記した。そもそも書評はその性格上、一方通行的になされることが多く、学術誌においても書評に対する査読は通常行われない。そのため、事実からかけ離れた「指摘」や、学術的客観性・公平性の担保されない「意見」「主張」ですらも、そのまま流通してしまいがちである。
書評は本来、その内容について書評執筆者が責任を負うべき著作物であるが、そうした自覚に乏しいものも散見される(岡崎氏の書評がそうだというのではない。念の為)。書評者の責任の自覚を喚起するには、書評に対する批評が不可欠であり、それがひいては書評全体のレベルを高めることにもつながるだろう。私はこれまで、自著への批評に対してはもっぱら沈黙してきたけれども、今後は上記のことを期待しつつ、なるべく積極的に応答してゆきたいと考えている。
末筆ながら、初期社会主義研究の大先輩である岡崎氏の、拙著に対する懇切かつ忌憚なき批評に、改めて感謝したい。
--------------------------------------------
(以下、2022年6月3日追記)
第一次『労働世界』について、私は上に、「『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという事実」と書いた。が、第一次『労働世界』は新聞であるか、雑誌であるかという問題について、さらに以下の注釈を付けておきたい。
第一次『労働世界』発刊前の1897年9月4日の労働組合期成会第二回月次会では「雑誌発行調査委員」が選ばれ、10月10日の第三回月次会で「雑誌社」の事業についての報告が可決されている(片山潜・西川光二郎『日本の労働運動』労働新聞社、1901年、第三編第一章第一節)。
ただしこれはあくまで発刊前の計画のことなので、実際に刊行された『労働世界』は計画と異なる、と見ることもできる。実際、「雑誌社」の事業は「労働新聞社」として実現したのである。そもそも新聞紙条例が適用される定期刊行物には「新聞」と「雑誌」の明確な区別基準がなく、体裁によって主観的に区別するしかない。体裁や当時の当事者自身の認識からすれば、本記事で書いたように、第一次『労働世界』は新聞とするのが適切であろう。
ただし、『日本の労働運動』の記述を重視するならば、第一次『労働世界』を雑誌とする見方も、誤りであるとまではいえないだろう。事実私も9年前の前著『日本社会民主主義の形成』では、第一次『労働世界』を雑誌として扱っていたことがあった。また本書の第5・6章は旧稿のため、この見解がそのまま残されている。本書の中に第一次『労働世界』を新聞とする見解と雑誌とする見解の両者が混在したままになっているのは、私自身のチェック不足であった。
いずれにせよ、上記の「『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという事実に基づく正しい表記である」という部分は、「『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという現在の有力な説に基づく表記である」と訂正されるべきであろう。
私は中国にいるので、当該号はしばらく入手できない。が、幸い同誌編集部の方が最終校正刷りのPDFファイルを送ってくださったので、書評を閲読することができた。
拙著を「初期社会主義研究に果敢に挑戦する刺激的好著」とする岡崎氏の評言はありがたく、当該分野における氏の長年の研究に基づく有益な指摘は尊重したい。ただし、氏の見解の中には、首をひねらざるを得ないもの、研究者としてとうてい承服できないものも少なくない。以下、岡崎氏の書評のうち疑問を感じる個所について、私からの応答を記しておきたい(なお『初期社会主義研究』30号の引用ページ数は最終校正刷りによる)。
私は拙著の序章4頁で、城多虎雄「論欧洲社会党」(『朝野新聞』1882年6~8月)について、「この論説は、「社会党ノ主義」=社会主義の理論と運動について、日本で初めて体系的に紹介したものといってよい」と記した。こうした私の評価について、岡崎氏は次のように批判している。
城多虎雄「論欧洲社会党」(『朝野新聞』一八八二年六~八月)の紹介に当り、〈この論説は、「社会党ノ主義」=社会主義の理論と運動について、日本で初めて体系的に紹介したものといってよい〉(四頁)と記しているが、久松定弘(編纂)『理想境事情 一名 社会党沿革』(進学舎、一八八二年二月)の方が先行しており、〈初めて〉という指摘は妥当ではないと考える。これは単純に著者が『明治文化全集』(日本評論新社)に拠っただけのことで、前記の久松や原田潜『自由提綱財産平均論』(春陽堂、一八八二年一一月)を翻刻している『明治文化資料叢書』第五巻社会主義編(風間書房)を見落としたためであろう。
(『初期社会主義研究』30号、260~261頁)
岡崎氏は、私があたかも『明治文化資料叢書』第5巻社会主義編を見落としたかのように推測しているが、理解に苦しむ。私はこの巻を持っているし、目を通してもいる。そもそも久松の『理想境事情』は、昔は稀覯本だったかもしれないが、今では国会図書館デジタルコレクションに収録されており、誰でも容易に閲読できる。確かに数十年前なら『明治文化全集』などの史料集に頼らざるを得ない研究状況があったのだろうが、史料へのアクセスが格段に向上している現在はそうではない。
久松の『理想境事情』と、城多の長大な論文「論欧洲社会党」との内容を比較すれば、両者の水準の差は明らかである。久松の『理想境事情』は、社会主義を単純に国民同権や財産平等分配の主張と同一視したうえで、ヨーロッパの社会主義者や運動を羅列的に紹介しているに過ぎない。対して城多の「論欧洲社会党」は、中等社会(ブルジョアジー)と労力社会(プロレタリアート)との対立から「近世文明」における社会主義発生の必然性を論じ、第一インターナショナルおよびドイツ・ロシア・フランス・イギリスの社会主義運動の発展過程をそれぞれ詳しく紹介したうえで、生産手段の共有と公平な分配という根本的主張に至る社会主義の論理を考察し、その主張の是非について独自の検討を加えている。
このように、社会主義の理論と運動史の体系的な把握において、城多の重厚な論考は久松の編著の薄っぺらな内容を圧倒しているのである。私が城多の論説を「社会主義の理論と運動について、日本で初めて体系的に紹介したもの」であると考える根拠はここにある。
なお、単に社会主義の理論と運動を紹介するだけであれば、久松の『理想境事情』よりはるか前の1878~79年に、『東京日日新聞』を始めとする在京の諸新聞がそれを活発に行っていたことは、拙著の第一章で詳論したとおりである。
また、拙著の序章で、1890年代初頭に特徴的な社会主義理解の例として、陸羯南と内藤湖南とを挙げたことについて、岡崎氏は次のように批判している。
政教社関係として陸羯南と内藤湖南にしか言及していない(四~五頁)が、この二人よりは「社会主義一斑」(『日本人』一八九四年三~五月)の筆者である長澤別天に言及する方が寧ろ妥当であろう。
(『初期社会主義研究』30号、261頁)
長澤別天の社会主義論については、私は前著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の第4章第1節で扱っているので、参照されたい。私がこのたび拙著の序章「近現代日本における「社会主義」概念の展開」を書くにあたっては、長澤よりも早い時期に書かれた陸・内藤の社会主義観の方にこそ、当時の「国民主義」・「国粋保存主義」に基づく独特な見解が色濃く現れていると考えてこれを紹介した一方、長澤の社会主義論は紙幅の関係上割愛したのである。
次に拙著第1章での、1878年12月の『横浜毎日新聞』における「社会党」論に関して、岡崎氏は次のように指摘している。
社会党に一定の理解を示す楠佐柄「社会党者流ガ処分」を社説として掲載した『横浜毎日新聞』(三頁)だが、これは一八七四年から当紙主筆を務め(一八七九年『東京横浜毎日新聞』と改称)一八八八年には社長となった島田三郎の存在抜きには考えられず、将来の島田の『世界之大問題社会主義概評』(一九〇一年)――『毎日新聞』(一八八六年改称)に連載した諸篇を纏めて単行化したもの――の発行を予兆したものと言えようか。
(『初期社会主義研究』30号、261頁)
島田三郎は、日本最初の日刊紙として明治三年十二月(1871年1月)に創刊された『横浜毎日新聞』の草創期である73年に入社し、翌年社員総代の島田豊寛の養子となった。ただし島田三郎は75年元老院に入って(のち文部省に移る)、いったん同紙から離れており、明治十四年の政変(81年10月)で免官された後、『東京横浜毎日新聞』に再入社している。したがって、1878年12月の『横浜毎日新聞』社説の内容が、「島田三郎の存在抜きには考えられ」ないという岡崎氏の断言は、根拠が疑わしく、首肯できない。
同じく拙著第1章で言及した『郵便報知新聞』の「社会党」論に関し、岡崎氏は次のように指摘する。
一八八二~九〇年には報知社社長も努めた矢野龍溪が、やがて西洋ユートピア文学の基準に照らしてみても遜色のない日本初の本格的なユートピア文学作品『新社会』(一九〇二年)と講演集『社会主義全集』(一九〇三年)を公表することになる史実は、(著者の視角には入ってはいないものの)実に興味深い。
(『初期社会主義研究』30号、261頁)
矢野龍渓は『郵便報知新聞』紙上で、「貧民救助法ヲ論ズ」(1876年6月8日)など社会問題に関係する社説を早い時期から書いており、後年の社会主義への関心とあわせて考えると、岡崎氏の指摘どおり確かに興味深いといえる。ただし、私は前著『日本社会民主主義の形成』第9章第2節および第4節で、1902年春から片山潜と矢野との交流が始まり、同年7月から矢野が社会主義協会の演説会に出演するようになったことや、片山の主宰する『労働世界』に「社会主義談」「四級団改善の急務」など矢野の談話・論説が掲載された事実を指摘し、また矢野のユートピア小説『新社会』を、それに対する木下尚江の批評とあわせて紹介している。したがって、「著者の視角には入ってはいない」などとする岡崎氏の決めつけはいただけない。
第4章「初期民友社の社会・労働問題論と「平民主義」─竹越与三郎を中心に」では、同じくヘンリー・ジョージを引用しながらも民友社内の竹越と徳富蘇峰では〈平民主義〉・〈社会問題〉の捉え方に差異があったことを指摘しているが、同じく「慈善事業の進歩を望む」(『評論』一八九四年六月五日)でジョージを引用した北村透谷との比較を付加すれば、更に興味深くなったことであろう。 (中略) 海外移民の問題も取り上げられているが、より広く文学畑の文献(内田魯庵「くれの廿八日」など)まで含めて論じてもらいたいものである。
(『初期社会主義研究』30号、261~262頁)
第4章での研究対象は、初期民友社の社会・労働問題論として1887年から1890年の時期に限定している。したがって、北村透谷の1894年の評論や、内田魯庵の小説「くれの廿八日」(1898年)は、本稿での比較検討の対象外である。
『労働世界』について〈同紙〉(二〇八頁一一行目)となっているが、これは〈同誌〉の誤記か誤植であろう。
(『初期社会主義研究』30号、262頁)
これは誤記でも誤植でもなく、『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという事実に基づく正しい表記である。労働組合期成会について最も詳細な研究をしてきた二村一夫氏も、次のように指摘している。「1897(明治30)年12月1日、労働組合期成会の機関紙『労働世界』が創刊されました。もともと機関紙の刊行は創立当初から計画され…」、「『労働世界』は、復刻版がサイズを縮小して刊行されたことなどから、しばしば「雑誌」と間違えられていますが、実際はタブロイド判の新聞でした」(「高野房太郎とその時代 (71)」『二村一夫著作集』(オンライン版))。
事実、当時の『労働世界』は当事者たちによって例外なく「新聞」と称されているのである(「鉄工組合本部臨時本部委員総会議事速記録」『労働世界』55号、1900年2月15日、附録第一~二面)。
片山潜が主筆を務めた『労働世界』は、第一次と第二次とに区別される。第一次『労働世界』は、労働組合期成会(および鉄工組合)の機関紙として1897年12月から1901年12月まで全100号が発行された、新聞体の定期刊行物である。他方、第二次『労働世界』は、1902年4月から1903年3月『社会主義』に改題されるまで発行された、雑誌体の定期刊行物である。岡崎氏はおそらく両者を混同しているのではあるまいか。
なお、当時の「新聞紙条例」には新聞と雑誌の明確な概念的区別はなく(どちらも新聞紙条例により取り締まりを受けた)、両者は主に体裁によって区別されていたといってよい(ただし雑誌のうち、「専ラ学術、技芸、統計、広告ノ類ヲ記載スル雑誌」については「新聞紙条例」ではなく「出版法」の規制を受けた)。
そして、岡崎氏の次のような私への〈アドバイス〉には看過できない問題がある。
蔑称(特に〈支那〉)に繰り返し〔ママ〕を傍記しているが、史料という観点からすると、一々傍記するよりも、寧ろ「凡例」で著者の見解として予め明確な断り書きを入れておけば良かったと考える。
(『初期社会主義研究』30号、263頁)
ここには、現在差別語として他者の尊厳を傷つける恐れのある歴史的語彙の扱いについての、岡崎氏と私との間に横たわる認識の落差がある。現在中国で歴史教育に携わっている私は、「支那」という語がその歴史的経緯のために、いかに中国の人びとの尊厳を傷つける言葉であるかを、痛切に理解している。だから、歴史的史料からの引用においても、当時の文脈におけるこの語の使われ方はどうであれ、この語が現在注記なしには決して用いられるべきではないことを示すために、繁雑をいとわずあえてこの語に〔ママ〕と傍記した次第である。この件について岡崎氏の考え方は私と異なるらしいが、氏の〈アドバイス〉を受け容れることはできない。
以上、拙著に対する岡崎氏の書評のうち、疑問を感じる箇所について私からの応答を記した。そもそも書評はその性格上、一方通行的になされることが多く、学術誌においても書評に対する査読は通常行われない。そのため、事実からかけ離れた「指摘」や、学術的客観性・公平性の担保されない「意見」「主張」ですらも、そのまま流通してしまいがちである。
書評は本来、その内容について書評執筆者が責任を負うべき著作物であるが、そうした自覚に乏しいものも散見される(岡崎氏の書評がそうだというのではない。念の為)。書評者の責任の自覚を喚起するには、書評に対する批評が不可欠であり、それがひいては書評全体のレベルを高めることにもつながるだろう。私はこれまで、自著への批評に対してはもっぱら沈黙してきたけれども、今後は上記のことを期待しつつ、なるべく積極的に応答してゆきたいと考えている。
末筆ながら、初期社会主義研究の大先輩である岡崎氏の、拙著に対する懇切かつ忌憚なき批評に、改めて感謝したい。
--------------------------------------------
(以下、2022年6月3日追記)
第一次『労働世界』について、私は上に、「『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという事実」と書いた。が、第一次『労働世界』は新聞であるか、雑誌であるかという問題について、さらに以下の注釈を付けておきたい。
第一次『労働世界』発刊前の1897年9月4日の労働組合期成会第二回月次会では「雑誌発行調査委員」が選ばれ、10月10日の第三回月次会で「雑誌社」の事業についての報告が可決されている(片山潜・西川光二郎『日本の労働運動』労働新聞社、1901年、第三編第一章第一節)。
ただしこれはあくまで発刊前の計画のことなので、実際に刊行された『労働世界』は計画と異なる、と見ることもできる。実際、「雑誌社」の事業は「労働新聞社」として実現したのである。そもそも新聞紙条例が適用される定期刊行物には「新聞」と「雑誌」の明確な区別基準がなく、体裁によって主観的に区別するしかない。体裁や当時の当事者自身の認識からすれば、本記事で書いたように、第一次『労働世界』は新聞とするのが適切であろう。
ただし、『日本の労働運動』の記述を重視するならば、第一次『労働世界』を雑誌とする見方も、誤りであるとまではいえないだろう。事実私も9年前の前著『日本社会民主主義の形成』では、第一次『労働世界』を雑誌として扱っていたことがあった。また本書の第5・6章は旧稿のため、この見解がそのまま残されている。本書の中に第一次『労働世界』を新聞とする見解と雑誌とする見解の両者が混在したままになっているのは、私自身のチェック不足であった。
いずれにせよ、上記の「『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという事実に基づく正しい表記である」という部分は、「『労働世界』が労働組合期成会の機関紙であるという現在の有力な説に基づく表記である」と訂正されるべきであろう。
2022-04-24 19:53
日本共産党の自衛隊「活用」論の歴史過程 [日本・現代社会]
日本共産党の志位委員長は4月7日、「参議院選挙勝利・全国総決起集会」において、ウクライナ情勢を踏まえて次のように述べた。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-04-08/2022040804_01_0.html
この発言がNHKや『読売新聞』などで報じられたことで、波紋が広がっている。
これについて、共産党は突然立場を変えたのかと訝しがる人もいれば、いや、これは綱領に沿う一貫した党の立場だ、という見方もある。実際のところは果たしてどうだろうか。
まず注意したいのは、日本共産党は敗戦直後から現在まで一貫して、日本国家が自衛権を保持することを正当なこととして主張してきたことだ。
1946年6月の衆議院本会議で日本国憲法草案の審議が行われた際、第9条の戦争放棄条項について、日本共産党政治局員の野坂参三は次のように主張した。戦争には日本の帝国主義者が起こしたような「侵略戦争」と、中国のように「侵略された国が自国を守るための戦争」すなわち「防衛的な戦争」(自衛戦争)とがある。前者は「不正の戦争」であるが、後者は「正しい戦争と言つて差支へないと思ふ」、したがって放棄すべきは侵略戦争であって自衛戦争ではない、と。それに対して吉田茂首相は、自衛戦争を認めるのは「戦争を誘発する有害な考へである」と答弁している(第90回帝国議会衆議院本会議第8号、1946年6月28日)。
他方、自衛隊については、共産党は1961年綱領(第8回党大会)で、「日本の自衛隊は……日本独占資本の支配の武器であるとともに、アメリカの極東戦略の一翼としての役割をおわされ」ており、「アメリカ帝国主義と日本独占資本は、自衛隊の増強と核武装化をすすめ、弾圧機構の拡充をおこない……軍国主義の復活と政治的反動をつよめている」として、「自衛隊の解散を要求」している。
日本共産党は、外国からの侵略に対する日本国家の武装的抵抗としての自衛を正当な権利として認める考えから、日本社会党の「非武装・中立」論とは異なる立場を取ってきた。1975年第12回党大会では、「民主連合政府綱領についての日本共産党の提案」の採択にあたり「急迫不正の侵略にたいして、国民の自発的抵抗はもちろん、政府が国民を結集し、あるいは警察力を動員するなどして、その侵略をうちやぶることも、自衛権の発動として当然」であり、「憲法第九条をふくむ現行憲法全体の大前提である国家の主権と独立、国民の生活と生存があやうくされたとき、可能なあらゆる手段を動員してたたかうことは、主権国家として当然」だとされた。
外部からの侵略に対し「可能なあらゆる手段を動員してたたかう」自衛権の保持の主張と、自衛隊否定の主張とを調和させることは、容易ではなかった。将来幅広い民主統一戦線を結集して「民主連合政府」が樹立され、アメリカ帝国主義を追い払い、日本が「独立・中立」の主権国家となったあかつきには、憲法9条はむしろ日本の独立・中立を守るのに必要な自衛権を制約しかねない。そこで9条を将来改定することも議論された。1980年5月の三中総で採択された「八〇年代をきりひらく民主連合政府の当面の中心政策」では、自衛隊解散に進む一方、「独立国として自衛措置のあり方について国民的な検討と討論を開始する」とされた。こうした共産党の安全保障政策方針は「中立・自衛」論と呼ばれる。
だが、冷戦終結後の90年代になると、このような共産党の「中立・自衛」論は転換されることになる。
1994年7月の第20回党大会の決議では、「憲法九条にしるされたあらゆる戦力の放棄は……わが党がめざす社会主義・共産主義の理想と合致したものである」という考えのもと、「わが国が独立・中立の道をすすみだしたさいの日本の安全保障」として「急迫不正の主権侵害にたいしては、警察力や自主的自警組織など憲法九条と矛盾しない自衛措置をとることが基本」だとしている。将来においても憲法9条を維持し、戦力を保持せず、「急迫不正」の侵略に対する自衛措置は非軍事的になされることが明記されたのである。
ところが、さらに大きな転換が、2000年11月の第22回党大会決議で行われた(https://www.jcp.or.jp/web_policy/2000/11/post-330.html )。この決議では、将来の「民主連合政府」において自衛隊問題を「段階的」に解決する方針を打ち出した。その第一段階は「日米安保条約廃棄前の段階」、第二段階は「日米安保条約が廃棄され、日本が日米軍事同盟からぬけだした段階」、第三段階は「国民の合意で、憲法九条の完全実施――自衛隊解消にとりくむ段階」であるとされる。
こうした「憲法九条の完全実施への接近の過程では、自衛隊が憲法違反の存在であるという認識には変わりがないが、これが一定の期間存在することはさけられない」として、次のように述べられている。
こうして日本共産党は、「自衛隊を国民の安全のために活用する」という主張を始めて打ち出したのである。その背景には、98年7月の参議院選挙の比例代表で共産党が過去最高の得票数を得たことで、政権に参加する道を模索する動きが出はじめたことがあるだろう。
ただし、「急迫不正の主権侵害」下での自衛隊の「活用」というのはあくまで、将来実現されるべき、日米安保条約と自衛隊を解消してゆく過渡期たる「民主連合政府」においてのことだとされていることに、注意せねばならない。このことについて、2003年8月に行われた講演で、志位委員長は次のように明言している。(https://www.shii.gr.jp/pol/2003/2003_08/2003_0826_1.html )
ところが2015年以降、この方針が変えられてゆく。2015年9月に安保法制が成立した後、日本共産党は安保法制を廃止するための政権交代を実現するため、安保法制廃止の一点で一致する政党・個人・団体による「国民連合政府」という連立政権構想を打ち出し、他の野党に選挙協力を呼び掛けた。なお、この「国民連合政府」というのが、日米安保廃棄など「民主主義革命」の課題を担う「民主連合政府」とは異なり、単に安保法制廃止の一点のみでまとまった連立政権として考えられていることは注意を要する。
この構想は、他の野党から懐疑や反対の声が出たために棚上げとなったが、これ以降「野党共闘」の選挙協力が行われるようになった。2016年7月の参院選に際し、日本共産党の「参院選法定2号ビラ」には次のように書かれている。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-01/2016070103_02_0.html
2000年の党大会決議では、「急迫不正の主権侵害」下での自衛隊の「活用」というのは、あくまで将来の「民主連合政府」でのことだとされていたのが、このビラではそれがあいまいになっている。2017年1月の第27回党大会の決議においても、次のように述べられている。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2017/01/post-746.html
自衛隊の「活用」は「民主連合政府」が将来樹立された後のことである、という2000年決議での限定が、この2017年の決議では消えてしまっている。前年の参院選での野党共闘に対しては、与党側から、自衛隊を違憲とする共産党と、立場の全く異なる他の野党とが共闘するのは「野合」だ、という非難が盛んになされた。そうした攻撃に対し、野党共闘の正当性を主張するための論理を作る中で、この決議が打ち出されていることに注目したい。ここでは、非自公政権に共産党が参加する場合、党は「急迫不正の主権侵害」に対する自衛隊の「活用」に反対しない、ということが示唆されているようにみえる。
今年2022年のはじめ、日本共産党は「あなたの「?」におこたえします」というパンフレットを作成し、将来共産党が政権に入った場合(あるいは閣外協力)、日米安保・自衛隊・天皇制など基本的な国策をどうするかを説明している(https://www.jcp.or.jp/web_download/202202-JCP-gimon.pdf )。その中で、「私たちは“安保条約の賛否”をこえて、皆さんと力をあわせます」、「与党になったら天皇制は廃止?そんなことは絶対にしません」などと明記するのとともに、自衛隊については次のように説明している。
このパンフレットに「民主連合政府」の文字はどこにもない。ここに読み取れるのは、共産党が非自公政権に参加した場合、あるいは閣外協力の場合でも、「急迫不正」の侵略に対しては自衛隊の武力行使を認める、ということである。パンフレットの末尾には、「安保条約や自衛隊など、他の野党と意見のちがう問題を政権には持ち込みません」と明記されている。
ここでもう一度、冒頭で挙げた今月7日の志位委員長の発言を検討しよう。
この志位発言には、従来の共産党の見解に新しく付け加えられたことがある。「急迫不正」の侵略に対して自衛隊を使用する目的は従来、「国民の生命と安全」を守ることとされていたのが、ここではさらに「日本の主権を守り抜く」ことがはっきりと付加されたことである。さらに、共産党の参加・協力する政権に限らず、現在の自公政権においても、「急迫不正の主権侵害が起こった場合」には、「個別的自衛権」の行使、すなわち「自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して、国民の命と日本の主権を守りぬく」のが共産党の立場だ、と宣言しているように読み取れるのである。
自衛隊の使用をめぐる今回の志位氏の発言の趣旨は、決して突然現れたものではない。その原型は、2000年の大会決議における党の方針転換において生まれたものであった。そしてその原型は以後、二十数年間の政治情勢の変化の中で徐々に変質を加えてゆき、ウクライナ戦争勃発による危機感の高まりによって、ついにここに至ったのである。
国会内政党の中で最も「左」に位置する共産党の自衛隊をめぐる見解の変化は、近年の国際情勢の変動に伴う日本の世論全体の動きを反映しているのであろう。ともかく今後、自衛隊の武力行使をめぐって、国会で「挙国一致」の状況が出現しないとも限らない。そういう悪夢だけは決して見たくないものだ。
憲法9条を生かした日本政府のまともな外交努力がないもとで、「外交だけで日本を守れるか」というご心配もあるかもしれません。それに対しては、東アジアに平和な国際環境をつくる外交努力によって、そうした不安をとりのぞくことが何よりも大事だということを、重ねて強調したいと思います。同時に、万が一、急迫不正の主権侵害が起こった場合には、自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して、国民の命と日本の主権を守りぬくというのが、日本共産党の立場であります。 (中略) ここで強調しておきたいのは、憲法9条は、戦争を放棄し、戦力の保持を禁止していますが、無抵抗主義ではないということです。憲法9条のもとでも個別的自衛権は存在するし、必要に迫られた場合にはその権利を行使することは当然であるというのが、日本共産党の確固とした立場であることも、強調しておきたいと思います。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-04-08/2022040804_01_0.html
この発言がNHKや『読売新聞』などで報じられたことで、波紋が広がっている。
これについて、共産党は突然立場を変えたのかと訝しがる人もいれば、いや、これは綱領に沿う一貫した党の立場だ、という見方もある。実際のところは果たしてどうだろうか。
まず注意したいのは、日本共産党は敗戦直後から現在まで一貫して、日本国家が自衛権を保持することを正当なこととして主張してきたことだ。
1946年6月の衆議院本会議で日本国憲法草案の審議が行われた際、第9条の戦争放棄条項について、日本共産党政治局員の野坂参三は次のように主張した。戦争には日本の帝国主義者が起こしたような「侵略戦争」と、中国のように「侵略された国が自国を守るための戦争」すなわち「防衛的な戦争」(自衛戦争)とがある。前者は「不正の戦争」であるが、後者は「正しい戦争と言つて差支へないと思ふ」、したがって放棄すべきは侵略戦争であって自衛戦争ではない、と。それに対して吉田茂首相は、自衛戦争を認めるのは「戦争を誘発する有害な考へである」と答弁している(第90回帝国議会衆議院本会議第8号、1946年6月28日)。
他方、自衛隊については、共産党は1961年綱領(第8回党大会)で、「日本の自衛隊は……日本独占資本の支配の武器であるとともに、アメリカの極東戦略の一翼としての役割をおわされ」ており、「アメリカ帝国主義と日本独占資本は、自衛隊の増強と核武装化をすすめ、弾圧機構の拡充をおこない……軍国主義の復活と政治的反動をつよめている」として、「自衛隊の解散を要求」している。
日本共産党は、外国からの侵略に対する日本国家の武装的抵抗としての自衛を正当な権利として認める考えから、日本社会党の「非武装・中立」論とは異なる立場を取ってきた。1975年第12回党大会では、「民主連合政府綱領についての日本共産党の提案」の採択にあたり「急迫不正の侵略にたいして、国民の自発的抵抗はもちろん、政府が国民を結集し、あるいは警察力を動員するなどして、その侵略をうちやぶることも、自衛権の発動として当然」であり、「憲法第九条をふくむ現行憲法全体の大前提である国家の主権と独立、国民の生活と生存があやうくされたとき、可能なあらゆる手段を動員してたたかうことは、主権国家として当然」だとされた。
外部からの侵略に対し「可能なあらゆる手段を動員してたたかう」自衛権の保持の主張と、自衛隊否定の主張とを調和させることは、容易ではなかった。将来幅広い民主統一戦線を結集して「民主連合政府」が樹立され、アメリカ帝国主義を追い払い、日本が「独立・中立」の主権国家となったあかつきには、憲法9条はむしろ日本の独立・中立を守るのに必要な自衛権を制約しかねない。そこで9条を将来改定することも議論された。1980年5月の三中総で採択された「八〇年代をきりひらく民主連合政府の当面の中心政策」では、自衛隊解散に進む一方、「独立国として自衛措置のあり方について国民的な検討と討論を開始する」とされた。こうした共産党の安全保障政策方針は「中立・自衛」論と呼ばれる。
だが、冷戦終結後の90年代になると、このような共産党の「中立・自衛」論は転換されることになる。
1994年7月の第20回党大会の決議では、「憲法九条にしるされたあらゆる戦力の放棄は……わが党がめざす社会主義・共産主義の理想と合致したものである」という考えのもと、「わが国が独立・中立の道をすすみだしたさいの日本の安全保障」として「急迫不正の主権侵害にたいしては、警察力や自主的自警組織など憲法九条と矛盾しない自衛措置をとることが基本」だとしている。将来においても憲法9条を維持し、戦力を保持せず、「急迫不正」の侵略に対する自衛措置は非軍事的になされることが明記されたのである。
ところが、さらに大きな転換が、2000年11月の第22回党大会決議で行われた(https://www.jcp.or.jp/web_policy/2000/11/post-330.html )。この決議では、将来の「民主連合政府」において自衛隊問題を「段階的」に解決する方針を打ち出した。その第一段階は「日米安保条約廃棄前の段階」、第二段階は「日米安保条約が廃棄され、日本が日米軍事同盟からぬけだした段階」、第三段階は「国民の合意で、憲法九条の完全実施――自衛隊解消にとりくむ段階」であるとされる。
こうした「憲法九条の完全実施への接近の過程では、自衛隊が憲法違反の存在であるという認識には変わりがないが、これが一定の期間存在することはさけられない」として、次のように述べられている。
憲法と自衛隊との矛盾を引き継ぎながら、それを憲法九条の完全実 施の方向で解消することをめざすのが、民主連合政府に参加するわが党の立場である。 / そうした過渡的な時期に、急迫不正の主権侵害、大規模災害など、必要にせまられた場合には、存在している自衛隊を国民の安全のために活用する。国民の生活と生存、基本的人権、国の主権と独立など、憲法が立脚している原理を守るために、可能なあらゆる手段を用いることは、政治の当然の責務である。
こうして日本共産党は、「自衛隊を国民の安全のために活用する」という主張を始めて打ち出したのである。その背景には、98年7月の参議院選挙の比例代表で共産党が過去最高の得票数を得たことで、政権に参加する道を模索する動きが出はじめたことがあるだろう。
ただし、「急迫不正の主権侵害」下での自衛隊の「活用」というのはあくまで、将来実現されるべき、日米安保条約と自衛隊を解消してゆく過渡期たる「民主連合政府」においてのことだとされていることに、注意せねばならない。このことについて、2003年8月に行われた講演で、志位委員長は次のように明言している。(https://www.shii.gr.jp/pol/2003/2003_08/2003_0826_1.html )
こうした自衛隊の段階的解消という方針は、民主連合政府と自衛隊が、一定期間共存することが避けられないということを意味します。このことから、一つの理論的設問が出てきます。そうした過渡的な時期に、万一日本が攻められたらどうするのか。この設問に対する私たちの答えは、そういうときには、動員可能なあらゆる手段を行使して、日本国民の生命と安全を守る、あらゆる手段のなかから自衛隊を排除しない、すなわち自衛隊も活用していくということが、私たちの答えです。
ところが2015年以降、この方針が変えられてゆく。2015年9月に安保法制が成立した後、日本共産党は安保法制を廃止するための政権交代を実現するため、安保法制廃止の一点で一致する政党・個人・団体による「国民連合政府」という連立政権構想を打ち出し、他の野党に選挙協力を呼び掛けた。なお、この「国民連合政府」というのが、日米安保廃棄など「民主主義革命」の課題を担う「民主連合政府」とは異なり、単に安保法制廃止の一点のみでまとまった連立政権として考えられていることは注意を要する。
この構想は、他の野党から懐疑や反対の声が出たために棚上げとなったが、これ以降「野党共闘」の選挙協力が行われるようになった。2016年7月の参院選に際し、日本共産党の「参院選法定2号ビラ」には次のように書かれている。
私たちは、自衛隊は憲法違反の存在だと考えています。同時に、すぐになくすことは考えていません。国民の圧倒的多数が「自衛隊がなくても大丈夫」という合意ができるまで、なくすことはできません。将来の展望として、国民の合意で9条の完全実施にふみだすというのが、私たちの方針です。 / それまでは自衛隊が存続することになりますが、その期間に、万一、急迫不正の主権侵害や大規模災害などがあった場合には、国民の命を守るために自衛隊に活動してもらう―この方針を党大会で決めています。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-01/2016070103_02_0.html
2000年の党大会決議では、「急迫不正の主権侵害」下での自衛隊の「活用」というのは、あくまで将来の「民主連合政府」でのことだとされていたのが、このビラではそれがあいまいになっている。2017年1月の第27回党大会の決議においても、次のように述べられている。
かなりの長期間にわたって、自衛隊と共存する期間が続くが、こういう期間に、急迫不正の主権侵害や大規模災害など、必要に迫られた場合には、自衛隊を活用することも含めて、あらゆる手段を使って国民の命を守る。日本共産党の立場こそ、憲法を守ることと、国民の命を守ることの、両方を真剣に追求する最も責任ある立場である。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2017/01/post-746.html
自衛隊の「活用」は「民主連合政府」が将来樹立された後のことである、という2000年決議での限定が、この2017年の決議では消えてしまっている。前年の参院選での野党共闘に対しては、与党側から、自衛隊を違憲とする共産党と、立場の全く異なる他の野党とが共闘するのは「野合」だ、という非難が盛んになされた。そうした攻撃に対し、野党共闘の正当性を主張するための論理を作る中で、この決議が打ち出されていることに注目したい。ここでは、非自公政権に共産党が参加する場合、党は「急迫不正の主権侵害」に対する自衛隊の「活用」に反対しない、ということが示唆されているようにみえる。
今年2022年のはじめ、日本共産党は「あなたの「?」におこたえします」というパンフレットを作成し、将来共産党が政権に入った場合(あるいは閣外協力)、日米安保・自衛隊・天皇制など基本的な国策をどうするかを説明している(https://www.jcp.or.jp/web_download/202202-JCP-gimon.pdf )。その中で、「私たちは“安保条約の賛否”をこえて、皆さんと力をあわせます」、「与党になったら天皇制は廃止?そんなことは絶対にしません」などと明記するのとともに、自衛隊については次のように説明している。
国民が「なくても安心」となるまでは存続/ 共産党は、いますぐ自衛隊をなくそうなどと考えていません。将来、アジアが平和になり、国民の圧倒的多数が「軍事力がなくても安心だ」と考えたときに、はじめて憲法9条の理想にむけてふみだそうと提案しています。 / 万が一、「急迫不正」の侵略をうけたら… /自衛隊もふくめて、あらゆる手段をもちいて命を守ります。国民の生存、基本的人権、国の主権と独立を守るのは、政治の当然の責務だからです。
このパンフレットに「民主連合政府」の文字はどこにもない。ここに読み取れるのは、共産党が非自公政権に参加した場合、あるいは閣外協力の場合でも、「急迫不正」の侵略に対しては自衛隊の武力行使を認める、ということである。パンフレットの末尾には、「安保条約や自衛隊など、他の野党と意見のちがう問題を政権には持ち込みません」と明記されている。
ここでもう一度、冒頭で挙げた今月7日の志位委員長の発言を検討しよう。
憲法9条を生かした日本政府のまともな外交努力がないもとで、「外交だけで日本を守れるか」というご心配もあるかもしれません。それに対しては、東アジアに平和な国際環境をつくる外交努力によって、そうした不安をとりのぞくことが何よりも大事だということを、重ねて強調したいと思います。同時に、万が一、急迫不正の主権侵害が起こった場合には、自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して、国民の命と日本の主権を守りぬくというのが、日本共産党の立場であります。 (中略) ここで強調しておきたいのは、憲法9条は、戦争を放棄し、戦力の保持を禁止していますが、無抵抗主義ではないということです。憲法9条のもとでも個別的自衛権は存在するし、必要に迫られた場合にはその権利を行使することは当然であるというのが、日本共産党の確固とした立場であることも、強調しておきたいと思います。
この志位発言には、従来の共産党の見解に新しく付け加えられたことがある。「急迫不正」の侵略に対して自衛隊を使用する目的は従来、「国民の生命と安全」を守ることとされていたのが、ここではさらに「日本の主権を守り抜く」ことがはっきりと付加されたことである。さらに、共産党の参加・協力する政権に限らず、現在の自公政権においても、「急迫不正の主権侵害が起こった場合」には、「個別的自衛権」の行使、すなわち「自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して、国民の命と日本の主権を守りぬく」のが共産党の立場だ、と宣言しているように読み取れるのである。
自衛隊の使用をめぐる今回の志位氏の発言の趣旨は、決して突然現れたものではない。その原型は、2000年の大会決議における党の方針転換において生まれたものであった。そしてその原型は以後、二十数年間の政治情勢の変化の中で徐々に変質を加えてゆき、ウクライナ戦争勃発による危機感の高まりによって、ついにここに至ったのである。
国会内政党の中で最も「左」に位置する共産党の自衛隊をめぐる見解の変化は、近年の国際情勢の変動に伴う日本の世論全体の動きを反映しているのであろう。ともかく今後、自衛隊の武力行使をめぐって、国会で「挙国一致」の状況が出現しないとも限らない。そういう悪夢だけは決して見たくないものだ。
2022-04-09 19:33
1896年徳富蘇峰の欧州旅行と青木周蔵書簡 [日本・近代史]
今学期の授業では、『徳富蘇峰関係文書』(全3巻、山川出版社)に収録された徳富蘇峰宛てのさまざまな書簡を学生たちといっしょに読んでいる。長春市は先月11日からすでに一か月近くロックダウンが続いており、大学キャンパスも封鎖されたままなので、オンライン授業となっているけれども。
幕末の動乱期に生まれ、明治維新から大日本帝国の滅亡に至る全過程を経験し、さらに新憲法制定、東西冷戦の開始、55年体制の成立を経て、亡くなるまでの蘇峰の95年の生涯は、近代日本の栄光と没落、光と闇とを体現するものといってよい。
蘇峰は1863年、肥後水俣の惣庄屋の家に生まれ、14歳で熊本バンド(日本プロテスタント・キリスト教の源流の一つ)の結盟に参加、京都の同志社英学校に学び、帰郷後は自由民権運動に参加した。さらに上京して1887年民友社を創立、雑誌『国民之友』と日刊『国民新聞』を創刊して「平民主義」を中心に平和・自由・進歩を説き、一躍論壇の寵児となった。が、日清戦争の頃から「日本膨張論」ついで帝国主義に転じ、「変節者」との罵声を浴びつつ藩閥政府に接近、『国民新聞』は桂太郎の機関紙となって日露戦争遂行に全面協力したあげく、その社屋は1905年の日比谷焼打事件で民衆に襲撃された。
韓国併合の1910年、蘇峰は朝鮮総督府の機関紙『京城日報』の監督となり、翌年には貴族院勅選議員に就任、皇室中心主義および「白閥打破」を唱えて大正デモクラシーに対抗した。31年の満洲事変後は軍部と結んで「興亜の大義」「挙国一致」を唱え、国民を戦争に動員する言論界の動きを主導した。40年、日独伊三国軍事同盟締結の建白書を近衛文麿首相に提出、41年には東条英機首相の依頼で「大東亜戦争」の「開戦の詔書」の作成に関与した。42年、大日本言論報国会会長に就任、43年文化勲章を受章。
45年敗戦後、蘇峰は「百敗院泡沫頑蘇居士」の戒名を自称、A級戦犯容疑者に名を連ねたが、高齢のため自宅拘禁となり、後に不起訴とされた。公職追放処分を受けて46年貴族院勅選議員を辞任、文化勲章を返上して、熱海に隠遁した。52年『近世日本国民史』全100巻を完結。57年死去。
95年に及ぶ長い生涯の間、蘇峰は新聞人として政財界・思想界・文学界・芸術界・学界の大物たちと交際している。自由民権期から戦後に至る、近代日本の各界の著名人から蘇峰に宛てられた膨大な数の書簡を蘇峰は保存していた。うち約4万6千通(差出人数約1万2千人)の書簡が、神奈川県二宮の徳富蘇峰記念館に所蔵されている。 その一部をまとめて公刊されたのが『徳富蘇峰関係文書』だが、大部分の書簡は未公刊のまま同館に眠っている。まさしく日本近代史・思想史の史料の宝庫といっていい。
その一部をまとめて公刊されたのが『徳富蘇峰関係文書』だが、大部分の書簡は未公刊のまま同館に眠っている。まさしく日本近代史・思想史の史料の宝庫といっていい。
今学期の授業では、藩閥官僚・政治家(青木周蔵・井上馨・井上毅・大隈重信・桂太郎・金子堅太郎・清浦奎吾)たちの蘇峰宛ての書簡を読んでいる。書簡の大部分は候文なので、その読み方の訓練を兼ねた授業である。中国の学生たちは漢文体の文語を読むのは得意だが、純和文体や候文はあまり読み慣れていない。ただし候文については、読み方のちょっとしたコツを教えると飲み込みが早く、やがてすらすらと読めるようになる。
先日は青木周蔵の書簡19通を読んだ。青木といえば、高校の日本史ではもっぱら条約改正(特に治外法権の撤廃)に尽力した外交官として登場するが、藩閥官僚政治家の中でもとくに過激な彼の侵略主義的外交思想については、あまり知られていないだろう。
1889年、青木は第一次山県有朋内閣の外相に就任した。山県首相は翌90年12月、第一回帝国議会の施政方針演説で、次のように主張した。国家の独立自営のためには、主権線(国境線)を守るだけではなく、その安全と密接に関係する地域=「利益線」の防護が重要である、と。「利益線」とは具体的に朝鮮を指す。日本の独立維持のためには朝鮮を影響下に置くことが必要というわけで、そのための軍拡予算の必要を山県は国会に訴えたのである。
ちなみにこの「利益線」という考え方は、ロシアが自らの独立維持に不可欠な勢力圏としてウクライナのNATO加盟を絶対に阻止しようと侵略戦争を起こした発想と、どこか似ている。
同じ1890年、青木周蔵外相は「東亜細亜列国ノ権衡」という意見書を提出した。それは山県の「利益線」論よりもさらに「積極的」=侵略的なものだ。この意見書の中で青木は、ヨーロッパが戦乱に入る時期を狙い、日本と清国が連合してロシアを討ち、朝鮮を日本の版図とし、さらに「満洲」(中国東北部)とカムチャッカをも日本の手中に収め、その代わりにシベリアを清国に与える、という外交政略を提言している。山県もびっくりの誇大妄想的な侵略思想だ。
さて、徳富蘇峰は1896年から97年にかけて欧米を旅行したが、当時の日本の知識人がもっぱら西欧に目を向けていたのに対し、蘇峰が東欧を重視したのは特徴的だ。彼はロシア帝国(ポーランドやウクライナを含む)、ルーマニア、オーストリア=ハンガリー帝国、トルコを巡遊し、ブカレストではルーマニア国王・首相のほか、たまたま来訪中のセルビア国王にも謁見している。ロシア帝国ではポーランドのワルシャワ、サンクトペテルブルク、モスクワのほか、ウクライナのキーウ(キエフ)とオデーサ(オデッサ)にも滞在した。
その間、蘇峰はヤースナヤ・ポリャーナのトルストイの屋敷を訪問し、親しく話をした。「人道」と「愛国心」とについて、トルストイは両立しないと言い、蘇峰は両立すると言った。蘇峰はトルストイ家で拾った木の葉を記念に持ち帰った。それを押し葉にした帳面は今も蘇峰記念館で見ることができる。なおトルストイは、日本の「雑誌編集者で大金持ち」「貴族」「聡明で自由思想の人」という蘇峰の印象について、モスクワの妻に宛てた手紙に書いている。
この旅行の途次、蘇峰はベルリンで駐独公使の青木に会った。互いに意気投合したようで、欧州旅行中の蘇峰に宛てて青木が書いた手紙が7通残されている。
うち、1897年4月20日付の青木の蘇峰宛書簡は興味深い。この手紙で青木は、日本の政界から体よく左遷されているわが身の不遇をかこち、自分の「不人望」について愚痴をだらだらと並べた後、自分自身の抱懐する外交政策を次のように披瀝している。
ここには、青木が長年抱いているというフィリピンに対する露骨な侵略の意図が、赤裸々に述べられている。そしてその手始めとして、日本人を数千または数万人移住させるという策を蘇峰に授けている。さらに青木は、陸軍の重鎮で日清戦争の際に征清総督府参謀長を務めた川上操六中将に宛てて、次のようなことづてを蘇峰に頼んだ。
「遼東鶏林〔鶏林は朝鮮の異称〕之恥辱」とは、日清戦争で分捕った遼東半島を露・仏・独の三国干渉によって手放さざるを得なくなったことと、閔妃暗殺事件後に朝鮮王宮が日本の影響力を排除しロシアを頼るようになったこととを指す。これらの「恥辱」をすすぐために、ロシアとの戦争準備を速やかにはじめる(それによって遼東と朝鮮を分捕る)べきだと、青木は提言しているのである。
この手紙の末尾に青木は次のように書いている。
幕末の動乱期に生まれ、明治維新から大日本帝国の滅亡に至る全過程を経験し、さらに新憲法制定、東西冷戦の開始、55年体制の成立を経て、亡くなるまでの蘇峰の95年の生涯は、近代日本の栄光と没落、光と闇とを体現するものといってよい。
蘇峰は1863年、肥後水俣の惣庄屋の家に生まれ、14歳で熊本バンド(日本プロテスタント・キリスト教の源流の一つ)の結盟に参加、京都の同志社英学校に学び、帰郷後は自由民権運動に参加した。さらに上京して1887年民友社を創立、雑誌『国民之友』と日刊『国民新聞』を創刊して「平民主義」を中心に平和・自由・進歩を説き、一躍論壇の寵児となった。が、日清戦争の頃から「日本膨張論」ついで帝国主義に転じ、「変節者」との罵声を浴びつつ藩閥政府に接近、『国民新聞』は桂太郎の機関紙となって日露戦争遂行に全面協力したあげく、その社屋は1905年の日比谷焼打事件で民衆に襲撃された。
韓国併合の1910年、蘇峰は朝鮮総督府の機関紙『京城日報』の監督となり、翌年には貴族院勅選議員に就任、皇室中心主義および「白閥打破」を唱えて大正デモクラシーに対抗した。31年の満洲事変後は軍部と結んで「興亜の大義」「挙国一致」を唱え、国民を戦争に動員する言論界の動きを主導した。40年、日独伊三国軍事同盟締結の建白書を近衛文麿首相に提出、41年には東条英機首相の依頼で「大東亜戦争」の「開戦の詔書」の作成に関与した。42年、大日本言論報国会会長に就任、43年文化勲章を受章。
45年敗戦後、蘇峰は「百敗院泡沫頑蘇居士」の戒名を自称、A級戦犯容疑者に名を連ねたが、高齢のため自宅拘禁となり、後に不起訴とされた。公職追放処分を受けて46年貴族院勅選議員を辞任、文化勲章を返上して、熱海に隠遁した。52年『近世日本国民史』全100巻を完結。57年死去。
95年に及ぶ長い生涯の間、蘇峰は新聞人として政財界・思想界・文学界・芸術界・学界の大物たちと交際している。自由民権期から戦後に至る、近代日本の各界の著名人から蘇峰に宛てられた膨大な数の書簡を蘇峰は保存していた。うち約4万6千通(差出人数約1万2千人)の書簡が、神奈川県二宮の徳富蘇峰記念館に所蔵されている。
今学期の授業では、藩閥官僚・政治家(青木周蔵・井上馨・井上毅・大隈重信・桂太郎・金子堅太郎・清浦奎吾)たちの蘇峰宛ての書簡を読んでいる。書簡の大部分は候文なので、その読み方の訓練を兼ねた授業である。中国の学生たちは漢文体の文語を読むのは得意だが、純和文体や候文はあまり読み慣れていない。ただし候文については、読み方のちょっとしたコツを教えると飲み込みが早く、やがてすらすらと読めるようになる。
先日は青木周蔵の書簡19通を読んだ。青木といえば、高校の日本史ではもっぱら条約改正(特に治外法権の撤廃)に尽力した外交官として登場するが、藩閥官僚政治家の中でもとくに過激な彼の侵略主義的外交思想については、あまり知られていないだろう。
1889年、青木は第一次山県有朋内閣の外相に就任した。山県首相は翌90年12月、第一回帝国議会の施政方針演説で、次のように主張した。国家の独立自営のためには、主権線(国境線)を守るだけではなく、その安全と密接に関係する地域=「利益線」の防護が重要である、と。「利益線」とは具体的に朝鮮を指す。日本の独立維持のためには朝鮮を影響下に置くことが必要というわけで、そのための軍拡予算の必要を山県は国会に訴えたのである。
ちなみにこの「利益線」という考え方は、ロシアが自らの独立維持に不可欠な勢力圏としてウクライナのNATO加盟を絶対に阻止しようと侵略戦争を起こした発想と、どこか似ている。
同じ1890年、青木周蔵外相は「東亜細亜列国ノ権衡」という意見書を提出した。それは山県の「利益線」論よりもさらに「積極的」=侵略的なものだ。この意見書の中で青木は、ヨーロッパが戦乱に入る時期を狙い、日本と清国が連合してロシアを討ち、朝鮮を日本の版図とし、さらに「満洲」(中国東北部)とカムチャッカをも日本の手中に収め、その代わりにシベリアを清国に与える、という外交政略を提言している。山県もびっくりの誇大妄想的な侵略思想だ。
さて、徳富蘇峰は1896年から97年にかけて欧米を旅行したが、当時の日本の知識人がもっぱら西欧に目を向けていたのに対し、蘇峰が東欧を重視したのは特徴的だ。彼はロシア帝国(ポーランドやウクライナを含む)、ルーマニア、オーストリア=ハンガリー帝国、トルコを巡遊し、ブカレストではルーマニア国王・首相のほか、たまたま来訪中のセルビア国王にも謁見している。ロシア帝国ではポーランドのワルシャワ、サンクトペテルブルク、モスクワのほか、ウクライナのキーウ(キエフ)とオデーサ(オデッサ)にも滞在した。
その間、蘇峰はヤースナヤ・ポリャーナのトルストイの屋敷を訪問し、親しく話をした。「人道」と「愛国心」とについて、トルストイは両立しないと言い、蘇峰は両立すると言った。蘇峰はトルストイ家で拾った木の葉を記念に持ち帰った。それを押し葉にした帳面は今も蘇峰記念館で見ることができる。なおトルストイは、日本の「雑誌編集者で大金持ち」「貴族」「聡明で自由思想の人」という蘇峰の印象について、モスクワの妻に宛てた手紙に書いている。
この旅行の途次、蘇峰はベルリンで駐独公使の青木に会った。互いに意気投合したようで、欧州旅行中の蘇峰に宛てて青木が書いた手紙が7通残されている。
うち、1897年4月20日付の青木の蘇峰宛書簡は興味深い。この手紙で青木は、日本の政界から体よく左遷されているわが身の不遇をかこち、自分の「不人望」について愚痴をだらだらと並べた後、自分自身の抱懐する外交政策を次のように披瀝している。
「老生は大臣時代に先〔さきだ〕ち既に呂宋〔ルソン〕を領略するの意ありて今尚ほ窃〔ひそか〕に之〔これ〕を抱持す……故に老兄若〔も〕し之〔これ〕を協賛するに意あらば西班牙〔スペイン〕人之〔の〕注意を惹起せざる様に運動して我同胞数千(数万なれば更に善し)を該島に出稼または移住する様に御駆引有之度〔これありたく〕候」
ここには、青木が長年抱いているというフィリピンに対する露骨な侵略の意図が、赤裸々に述べられている。そしてその手始めとして、日本人を数千または数万人移住させるという策を蘇峰に授けている。さらに青木は、陸軍の重鎮で日清戦争の際に征清総督府参謀長を務めた川上操六中将に宛てて、次のようなことづてを蘇峰に頼んだ。
「日本は来年(今年と申さば無理ならん)に至り露と戦ふの準備あるや。遼東鶏林之恥辱を雪〔すす〕ぐに意あるは老生之確信する処なれども果〔はたし〕て然らば速〔すみやか〕に準備を整ふべし。……と窃〔ひそか〕に御伝可被下〔おつたえくださるべく〕候」
「遼東鶏林〔鶏林は朝鮮の異称〕之恥辱」とは、日清戦争で分捕った遼東半島を露・仏・独の三国干渉によって手放さざるを得なくなったことと、閔妃暗殺事件後に朝鮮王宮が日本の影響力を排除しロシアを頼るようになったこととを指す。これらの「恥辱」をすすぐために、ロシアとの戦争準備を速やかにはじめる(それによって遼東と朝鮮を分捕る)べきだと、青木は提言しているのである。
この手紙の末尾に青木は次のように書いている。
「秘密々々御一見後御焼棄可被下〔くださるべく〕候」読み終わったら手紙を焼き捨てるよう、蘇峰に頼んでいるのである。しかしどういうわけか、蘇峰は青木の指示に従わず、この「秘密」の手紙をわざわざ日本まで持ち帰り、大切に保管した。その結果、青木の恐るべき侵略思想が、その愚痴もふくめて永遠に記録され、125年後に中国で授業の教材にされることになるとは、青木も蘇峰も想像すらしなかったであろう。
2022-04-08 21:46