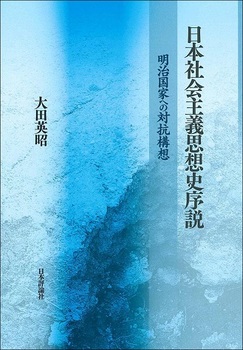二村一夫氏の反論に答えるーー「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって [日本・近代史]
明治時代の総合雑誌として著名な『国民之友』の95号(1890年9月23日)の社説欄に掲載された無署名の論説「労働者の声」は、日本で最初に労働組合の結成の必要を説いた文章の一つとして知られている。
日本の労働運動史上、記念碑的な意義をもっているこの論説は、いったい誰が書いたのだろうか?それについては古くから疑問とされ、詮索が行われてきた。
1952年、歴史家の家永三郎氏はこの疑問を解決すべく、晩年の徳富蘇峰(『国民之友』の創刊者・主宰者・主筆)のもとを訪れた際に、「労働者の声」の筆者について直接質問した。そのとき蘇峰は、これは自分が執筆したものでなく、竹越〔与三郎、号は三叉〕か山路〔愛山〕のものであろう、と明言したという(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』55号、1952年12月)。
この重要な証言を踏まえつつ、日本近代思想史研究者の佐々木敏二氏は、「労働者の声」の筆者について、山路愛山の筆とは考えにくく、竹越三叉の可能性が高いと推定しつつも、それを断定する決め手はないとしている(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収))。私もおおむね佐々木氏の説に与するものである。
ところが近年、労働史研究者の二村一夫氏が、その筆者を高野房太郎とする説を唱えている(二村一夫『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』〔岩波書店、2008年〕98~102頁)。なお、ほぼ同じ趣旨の文章が、WEB版『二村一夫著作集』第6巻の「高野房太郎とその時代(38)」にある)。
私は、二村氏の説は根拠に乏しいものと考え、拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) において、氏の説に批判を加えたうえで、「労働者の声」の筆者は竹越である蓋然性が高いことを指摘した。(この注の全文は、文章を若干手直ししたうえで、本ブログ2014年5月5日の投稿「「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者について」の中に再録してある。)
二村氏は最近、WEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「再論・「労働者の声」の筆者は誰か?─大田英昭氏に答える(1)─」と題する文章を公開し、私の批判に対する反論を試みている。
以下、本ブログ記事では、二村氏の反論が果たして妥当なものかどうか検討を加えたうえで、二村氏の主張する「労働者の声」の筆者=高野房太郎説がとうてい成り立ち得ない理由を改めて示しておきたい。
【1.家永三郎氏の聞き取りによる蘇峰証言をめぐって】
二村氏は、その著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』で、上記の家永氏の聞き取りによる蘇峰証言という重要史料の存在を見過ごすという大きなミスを犯している。拙著における私の批判点の一つはここにあったが、二村氏はご自身の誤りを率直に認めたうえで、さらに次のような議論を提起している。
---------------(引用はじめ)
この蘇峰証言で、確かな事実として認めて良いのは、「自分が筆をとつて書いたのではない」という箇所です。これは本人が、その論文を読んだ上で確言しているのですから、信頼してよいと思います。これによって、嘉治隆一が「徳富の起筆にかゝると伝へられる」と記した伝聞が誤りであることは確定した、と言って良いでしょう。
しかし、証言の後半部分、「竹越か山路であらう」という箇所は、「あらう」という言葉からも明白なように、蘇峰の推測による判断です。「労働者の声」の筆者を特定しているわけではなく、断定もしていません。竹越三叉か山路愛山の執筆であろうと、その蓋然性を述べているに過ぎません。このとき蘇峰は、「労働者の声」の「劈頭の部分を熟視して」はいますが、他に日記やメモを参照した様子はありません。つまり、89歳の徳富蘇峰が、27歳の時に編集刊行した『国民之友』に掲載した一論文の筆者について、記憶だけを頼りに答えたものです。蘇峰は、『国民之友』の論説記者のうち、こうした分野について書き得た人物は竹越三叉か山路愛山しかいなかったと考え、このように答えたものでしょう。おそらくこの時、蘇峰が、社外執筆者の存在に思い及ぶことは、なかったと思われます。なぜなら、家永三郎氏の質問は、「〈労働者の声〉が蘇峰の執筆か、他の同人の筆か、後者ならば誰の筆に成るものか」だったからです。この問いについては、前掲の「『国民之友』研究の思い出」に記されています。要するに、質問者も回答者も、最初から社外執筆者の存在を考慮していないのです。いずれにせよ、家永三郎氏の問いに対する蘇峰の回答が、さらなる検討を要するものであることは明白です。
---------------(引用おわり)
ここで二村氏が提起する論点は二つある。一つは、蘇峰証言における「竹越か山路であらう」という部分は、蘇峰の推測による蓋然性を述べているに過ぎないということ。もう一つは、家永氏と蘇峰との問答は、最初から社外執筆者の存在を考慮していないもので、この点は再検討を要するということ。
第一の論点からみよう。蘇峰証言が「労働者の声」の筆者を断定するものではなく、「蓋然性を述べている」ということについては、私もそのように考えており、異存はない。ただし、ここで蘇峰が、ともかく竹越と山路という二人の名前を明言した事実は、『国民之友』の社説欄がいかなるものだったかを考えるうえで、重要な示唆を与えている(後述)。
第二の論点に移ろう。家永氏と蘇峰との問答は、「労働者の声」の執筆者として「社外執筆者」が存在する可能性を念頭に置いていないことにそもそも問題がある、ということを二村氏は言いたいらしい。つまり二村氏は、家永氏も蘇峰も全然考えてもみなかった「社外執筆者」なるものが存在する可能性を主張している。だが二村氏の議論は、民友社(『国民之友』の発行主体)と何の関係もない高野房太郎が『国民之友』の社説を執筆したなどという、ありそうにもないことの可能性を残しておきたいためにする、無理筋の主張にすぎない。
「労働者の声」は、『国民之友』の「国民之友」欄に掲載された論説である。家永氏はこの「国民之友」欄について次のように説明している。「無署名であって、民友社の主義主張を発表する場所であり、蘇峰の政治的抱負を吐露するための欄である。従って大部分は蘇峰の執筆にかかると思われるが、なかには他の社員が執筆した文もあった」(「『国民之友』」『文学』23号、1955年1月)。また『国史大辞典』には北根豊氏による次の説明がある。「「国民之友」欄は社説欄に該当するところで、無署名であるが民友社すなわち蘇峰の主義主張を掲げた」(『国史大辞典』第五巻〔吉川弘文館、1985年〕)。
「国民之友」欄に掲載された論説は『国民之友』の社説であり、蘇峰ないし蘇峰に代わる民友社員の記者が無署名で執筆し、民友社の主義主張を掲げたものである、という見解は、現在に至るまで、『国民之友』を史料として研究する者の共通認識であろう。例えば、民友社研究で著名な西田毅氏がその著書『竹越与三郎』〔ミネルヴァ書房、2015年〕で、「民友記者として重用された三叉は、蘇峰とともに『国民之友』と『国民新聞』の社説を書いたが、のちに人見一太郎も三叉が書く社説の一部を執筆するようになった。『国民之友』の方は山路愛山も書くようになったという」(64頁)と記しているのも、同様の認識によるものだろう。
「労働者の声」が掲載された『国民之友』95号(1890年9月23日)の原本の縮刷版を確認すると、本号の「国民之友」欄に掲載された社説は「主動者の責任」(1~6頁)と「労働者の声」(6~11頁)の二編であり、ともに民友社の主義主張を掲げる社説としてふさわしい堂々たる内容と分量を備えている。
「労働者の声」をめぐる家永氏との問答で、蘇峰が「これは自分が筆を取つて書いたのではない、竹越か山路であらう、とはつきり答へた」のは、単に漠然と「蓋然性を述べている」にとどまらない。『国民之友』の社説の執筆者は、蘇峰か、蘇峰でなければ竹越・山路といった民友社員の主要な論説記者に限られていたという事実を、当事者たる蘇峰が示唆したものとみるべきではないだろうか。(ただし、山路の民友社入社は1892年であり、1890年の段階では『国民新聞』の寄稿者に過ぎなかった。社説の執筆者としては、他の民友社員の可能性も考える必要があるかもしれない。)
『国民之友』社説の位置づけをめぐって当事者や研究者の間で長年共有されてきた事実認識を、二村氏があえて疑い、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)などという主張を維持したいのであれば、まず『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を挙げることが、最低限必要だろう。さもなければ、「労働者の声」の筆者=高野房太郎説は、二村氏の願望の表現にすぎないといわねばならない。
【2.「労働者の声」竹越三叉執筆説をめぐって】
二村氏は、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と断定的に述べている。その根拠を二村氏は二つ挙げている。一つは「文体の違い」であり、もう一つは「文章の内容」である。
2.1 「文体」をめぐる問題
まず「文体の違い」について、二村氏の述べているところを検討しよう。
二村氏は、竹越の文章を山路愛山が「荘重典麗」と評したことを引きつつ、「竹越三叉の文章は、独特の形容を駆使し、多様な語彙を用いて、特有のリズム感をもっている」と述べる。そのうえで、名文家・美文家として知られた竹越の「荘重典麗」な文体の実例として、『新日本史(中巻)』(1892年)、「近日の文学」(『国民新聞』1890年5月16日〔二村氏が1893年としているのは書き間違いであろう〕)の一部を引き、また比較的説明的な文章の例として『人民読本』(1901年)を引いて、「「抑揚の妙を極めた散文詩」とか「荘重典麗」と言うには程遠い、理詰めの文章」である「労働者の声」とは文体が異なっていると、二村氏は主張している。
だが、二村氏のこうした比較の仕方に説得力はない。竹越が能文家であることは有名だが、そもそも能文家とは、単に〈荘重典麗〉な美文を書くだけでなく、文章の目的やそれを掲載する媒体に合わせてさまざまな種類の文体を駆使する能力をもっている。竹越の膨大な論説の中から都合のよいものを恣意的に引っ張ってきて、それを「労働者の声」の文体と表面的に比較し、文体が異なることをもって、「竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」ことを主張する根拠になるなどと、二村氏は本気で考えているのだろうか?
竹越は「労働者の声」が書かれたのと同じ1890年の初めに民友社に入社し、とりわけ『国民新聞』社説ならびに論説記事を担当する記者として活躍した(西田、前掲書)。そもそも『国民新聞』は、当時の新聞界が知識人向けの政論新聞である「大新聞」と庶民向けの娯楽的な「小新聞」とに棲み分けられていた状況で、多面性と平易性を併せ持つ「中新聞」として蘇峰が企画し創刊したものであった(有山輝雄『徳富蘇峰と国民新聞』〔吉川弘文館、1992年〕10~15頁)。そのような「中新聞」を中心的に担う論説記者として、竹越は多くの無署名記事を執筆したのである。
私も二村氏にならって、竹越の執筆した『国民新聞』論説の中から恣意的に選び出してみよう。以下に引用するのは、「下層社会の智見を啓発するの一手段」(『国民新聞』1891年6月29日)(『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』〔三一書房、1985年〕所収)という記事である。
「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか、是れ第一の社会問題也。如何にして下層社会の智見を開発すべきか、是れ第二の社会問題也。第一問題を講ずるものは必らず第二問題に及ぼさざるべからず。吾人は此に下層社会の智見を啓発するの一案として、手軽るき書籍館を開かんことを望む。現今上野に政府の図書館あり、神田に私立の書籍館ありと雖も、是等は多くは学者の考証、若しくは銭なき書生を目当とする者にして、其蔵する所の書籍も多くは此目的に適したる者也。且つ其学問を目当として遊楽を目当とせざるや、朝の八九時に初りて夕の五時に終る、夕の五時は正さに是れ下層社会にある者が、営々として道途に汗絞るの時也。到底今日の書籍館を以て、下層社会を啓発するの用に供するに足らざる也。書生学者は自ら求めても智識を研くべし。種々なる便宜を与へて之を誘ふは、下層社会に於てこそ要ある也。吾人は神田、芝、日本橋若しくは地方の小都会に於て、社会改良に志ある者が一個の手軽き書籍館を設け朝より開館して夕の九時までも開き、普通学の一斑、卑賤より立身したる大人物の伝記、歴史の一斑、世界事情旅行記、清潔なる小説、新体詩、等を集めて丁稚、小僧、労働者等の智見を開発するに便ならしめんことを望む。」
上の記事の文体と、二村氏が引用した同じ『国民新聞』での竹越の記事「近日の文学」の〈荘重典麗〉な文体とを比較すれば、竹越が多様な文体を状況に合わせて駆使できる能文家であったことが理解できるだろう。なお、上の記事にある「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか」という「第一の社会問題」についての竹越の言及は、内容的に「労働者の声」に通じるものとして注目すべきだろう。
2.2 「文章の内容」をめぐる問題
次に、竹越の著作と「労働者の声」とは「文章の内容」において異なる、という二村氏の主張を検討しよう。
二村氏は次のように述べている。
----------------(引用はじめ)
周知のように竹越与三郎は『新日本史』、『二千五百年史』、『日本経済史』など大部の通史・史論を刊行し、また『国民之友』をはじめ『六合雑誌』『国民新聞』『世界之日本』など数多くの雑誌・新聞に、多数の論稿を執筆しています。しかし、これらの著書や論稿のどこを探しても、「労働者の声」の筆者であれば、当然、論ずるであろう、労働問題に関する言及がないのです。
----------------(引用おわり)
二村氏は「これらの著書や論稿のどこを探しても…(中略)…労働問題に関する言及がない」と断言しているが、それは正しくない。
例えば、「経済書と聖書」(『六合雑誌』110号、1890年2月15日)という竹越の文章を次に引用しよう(引用に際し、原文の句読点を改めてある)。
「今日の文明は、実に物質的文明の大に発達せるときなり。凡そ二三十年前の人が夢にも幻にも知らざりし事多く今日に行はれ、取り分け生産力、即ち物を作り出す力大に発達せり、例せば紡績器、若しくは活版器械は、蒸気器の如し、此等は器械が一振するや、数百千の工夫が汗水垂らして働くよりも、多量なる物品を製出す。…(中略)…其富なるものは、僅に少数の人々の手に入りて、其他の多数は、以前として貧しく、富と云ふ太陽は背の高き大金持の頭を照らすも、背の低き、小商人、小農夫、労働者の頭を照らすことなし。…(中略)…見よ、鉄道は長く日本を貫ぬく、然れども鉄道のために、無数の民は其職業を失す。見よ、製造会社は立つ、之がために無数の細民は其業を擲つ。…(中略)…今日の文明は、僅かに其富の製産のみを実行して、社会の富を、地主に、金利に、労働者の賃金に、農夫の所得に、分配を適宜にするの方を講ぜず。」
上の文章は「労働者の声」の七か月前のものだが、社会問題に対する竹越の関心のなかに、生産の機械化・巨大化に伴う失業の深刻化や、労資間の分配の不公平など、労働問題への視点の萌芽が表れていることは、ある程度見て取ることができる。
また、「国家社会主義」(『世界之日本』第2巻第2号、1898年9月17日)(前掲『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』所収)で、竹越は次のように述べている。
「第三級民は、決して生活の自由を有せず。彼等は其労力に相当なる賃金を受る能はず。彼等は安楽に其家族を養ふ能はず。…(中略)…殊に製造所の持主と職工との関係に至りては最も甚し。製造所の持主は、固より資本家なるが故に、其利益によりて更らに其事業を拡張し、其利益を増進するの道あるに引きかへて、職工は日々の所得によりて衣食し、衣食に費したる残余は幾何もあらず。而して時として疾病あり、時として災難あり、遂に一年を平均して何の貯蓄する所なきに至る。夫れ製造所の主人の資本が富なるが如く、職工の労力のまた一種の富也。然るに一方は其富を倍加しつゝ行く間に、一方は依然として其富を加ふる能はざるのみならず、遂に其労働の結果として、衰病を得て死し、家に一物を止めず、妻子離散、或は人の門によりて食を乞ひ、甚しきは転じて売淫窟に堕落するに至りては、豈に傷心の極ならずや。我輩は多くの職工の境遇は其血肉を売つゝ資本家の事業を経営する者なりと云ふの適当なるを見る。」
上の論説には、明白に「労働問題に関する言及」をみることができる。労働問題への関心は、強弱の差こそあれ、少なくとも1890年代の竹越の論説の中にしばしばみられるのである。
『国民之友』には、「労働者の声」以後も、労働問題を論じた社説がしばしば現れる。例えば、「平民主義第二着の勝利」(139号、1891年12月13日)、「社会立法の時代」(157号、1892年6月13日)、「社会問題の新潮」(169号、1892年10月13日)などである。これらの社説は、労働組合・八時間労働制・職工条例・ストライキなど、労働問題を具体的に論じたものである。また『国民新聞』にも、「政治上に於ける社会主義」(1892年7月27日)、「聯合追放」(1892年10月28日)、「労働問題」(1892年12月8日)、「工場の立法」(1892年12月25日)など、労働問題をテーマとする社説は少なくない(佐々木敏二「『国民之友』における社会問題論」『キリスト教社会問題研究』(18号、1971年3月)を参照)。これら『国民之友』『国民新聞』の社説はいずれも無署名であるが、社説を執筆する可能性のある民友社記者のなかでも、竹越は社会問題・労働問題に早くから関心を抱いていた以上、彼がこれらの社説にも関わっている可能性については今後検討する余地がある。
2.3 小括
以上検討してきたように、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と二村氏が主張する二つの根拠(竹越の文章と「労働者の声」との文体の違い、および両者の内容の違い)は、いずれも説得力を欠いている。したがって、二村氏の主張は客観的に支持され得ないものと結論できる。
【3.「労働者の声」高野房太郎執筆説が成り立ち得ない理由の追加】
【1】で述べたように、二村氏の「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)という主張が、そもそも歴史学的に検討の余地のある仮説として成り立つには、『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を、二村氏自身が明示することが最低限必要である。だが二村氏はそれを全く明示できていない。
また、二村氏が「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という主張の根拠として挙げている四点が、いずれも根拠として薄弱であることについては、すでに拙著で説明したとおりである(本ブログ記事を参照)。
以上の理由だけでも、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という二村氏の主張がもはや存立の余地のないことは明白だろう。
さらにここでは、「労働者の声」の文章の内容からみても、高野房太郎が筆者であるとは考えがたい理由を、一つ付け加えておきたい。
「労働者の声」の一節を下に引用する。
「米国の如きも、ナイト、オフ、レバー(労働的の武士)なる者あり。其初や一種の秘密結社にして、其党員は皆暗語を有し、その徽号を有し、隠然たる運動を為せり。而して其勢力漸次に増加し、五年前に於ては、既に二百万人の会員を有するに至れり。亦盛なりと云ふべし。」
ここで言及されている「ナイト、オフ、レバー」とは、1869年にフィラデルフィアで創立された労働団体の労働騎士団(Knights of Labor)のことである。二村氏は『明治日本労働通信』(岩波書店、1997年)の注のなかで、労働騎士団は1886年に最盛期に達したものの、同年のヘイマーケット事件やアメリカ労働総同盟(American Federation of Labor, AFL)の結成によって打撃を受け、急速に衰退していった旨を記している。
「労働者の声」における労働騎士団への言及は、「五年前」すなわち同団体の衰退前の情報を用いていることが明らかである。
一方、1890年当時アメリカに滞在中で、当地の労働運動を注視していた高野は、それよりもはるかに新しい情報に接する立場にあった。事実、高野がワシントン州タコマから1890年4月に『読売新聞』に寄稿した論説「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」(同年5月31から6月27日にかけて連載)には、アメリカ労働運動の最新の情報を次のように記している。
「今や米合衆国中において最も有力なる二個の会合、すなわち五十九万余人を率いるアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアー及び三十余万の会員を有するナイト・オフ・レーボアーは、本年五月一日を期し互いに連合して八時間労働請求の運動を為さんとす」(前掲『明治日本労働通信』所収、275頁)。
高野はAFLが最有力の労働団体として五十九万余人を擁し、労働騎士団はそれに次ぐ三十余万に過ぎないことを書いており、1890年5月1日の記念すべき第一回メーデーの予定まで熟知していた。彼は、「千八百八十六年十二月合衆国中における五十九個の労役者の会合が合してアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアーを形造」(同上書、276頁)ったことを、労働組合運動の強化の方向として重視していたのである。
二村氏によれば高野が「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」を日本に向けて投函したのは4月30日である(二村、前掲『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』93頁)。仮に高野が「労働者の声」の筆者だとすると、「労働者の声」の執筆は「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」の投函から少し後のはずである。とすれば、なぜ「労働者の声」ではわざわざ五年前の古い情報に基づいて労働騎士団だけを紹介し、AFLについては全く言及しないのだろうか?なぜ第一回メーデーなどの最新の情報を伝えないのだろうか?全く不可解というほかない。このことも、「労働者の声」を高野が執筆した可能性が否定されるべき理由の一つである。
私は、高野の「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」や、「日本に於ける労働問題」(『読売新聞』1891年8月7~10日)は、アメリカで労働組合運動に接し、労働問題について深く考察した高野でなければ書くことのできない稀有の論説だと思う。だが「労働者の声」は、高野でなくとも、日本で欧米の労働問題に関心を持ち、欧米から流れてくる書籍や新聞の情報に接する立場にある者なら、書くことができる内容であると考える。
追記:
私は中国在住のため、このブログ記事を書くにあたり、手持ちの乏しい史料と研究書・論文、および国会図書館デジタルコレクションでオンライン公開されている史料を用いるにとどまり、今回参照したくてもできなかった研究や史料が少なくない。したがって、「労働者の声」の筆者を確定するにはまだ程遠い状態にある。竹越あるいは他の民友社員の可能性を含め、「労働者の声」の筆者をめぐるさらなる追究は今後の課題としたい。
追記2:
文章の一部を補訂しました(2018年5月14日・5月15日)
追記3:
ここでの拙論に対する反論として、二村氏は2018年5月20日、WEB版『二村一夫著作集』に「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(3)」を掲載しました。それに対する私からの再批判として、本ブログに下の一連の論稿をアップしたので、ご参照ください(2018年6月18日)
①再び二村一夫氏の反論に答える(1)
②再び二村一夫氏の反論に答える(2)
③再び二村一夫氏の反論に答える(3・完)
日本の労働運動史上、記念碑的な意義をもっているこの論説は、いったい誰が書いたのだろうか?それについては古くから疑問とされ、詮索が行われてきた。
1952年、歴史家の家永三郎氏はこの疑問を解決すべく、晩年の徳富蘇峰(『国民之友』の創刊者・主宰者・主筆)のもとを訪れた際に、「労働者の声」の筆者について直接質問した。そのとき蘇峰は、これは自分が執筆したものでなく、竹越〔与三郎、号は三叉〕か山路〔愛山〕のものであろう、と明言したという(家永三郎「「労働者の声」の筆者」『日本歴史』55号、1952年12月)。
この重要な証言を踏まえつつ、日本近代思想史研究者の佐々木敏二氏は、「労働者の声」の筆者について、山路愛山の筆とは考えにくく、竹越三叉の可能性が高いと推定しつつも、それを断定する決め手はないとしている(佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』〔雄山閣、1977年〕所収))。私もおおむね佐々木氏の説に与するものである。
ところが近年、労働史研究者の二村一夫氏が、その筆者を高野房太郎とする説を唱えている(二村一夫『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』〔岩波書店、2008年〕98~102頁)。なお、ほぼ同じ趣旨の文章が、WEB版『二村一夫著作集』第6巻の「高野房太郎とその時代(38)」にある)。
私は、二村氏の説は根拠に乏しいものと考え、拙著『日本社会民主主義の形成―片山潜とその時代』(日本評論社、2013年)の「第4章 日本における「社会問題」論の形成」の注(73) において、氏の説に批判を加えたうえで、「労働者の声」の筆者は竹越である蓋然性が高いことを指摘した。(この注の全文は、文章を若干手直ししたうえで、本ブログ2014年5月5日の投稿「「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者について」の中に再録してある。)
二村氏は最近、WEB版『二村一夫著作集』の「高野房太郎とその時代」の追補として、「再論・「労働者の声」の筆者は誰か?─大田英昭氏に答える(1)─」と題する文章を公開し、私の批判に対する反論を試みている。
以下、本ブログ記事では、二村氏の反論が果たして妥当なものかどうか検討を加えたうえで、二村氏の主張する「労働者の声」の筆者=高野房太郎説がとうてい成り立ち得ない理由を改めて示しておきたい。
【1.家永三郎氏の聞き取りによる蘇峰証言をめぐって】
二村氏は、その著書『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』で、上記の家永氏の聞き取りによる蘇峰証言という重要史料の存在を見過ごすという大きなミスを犯している。拙著における私の批判点の一つはここにあったが、二村氏はご自身の誤りを率直に認めたうえで、さらに次のような議論を提起している。
---------------(引用はじめ)
この蘇峰証言で、確かな事実として認めて良いのは、「自分が筆をとつて書いたのではない」という箇所です。これは本人が、その論文を読んだ上で確言しているのですから、信頼してよいと思います。これによって、嘉治隆一が「徳富の起筆にかゝると伝へられる」と記した伝聞が誤りであることは確定した、と言って良いでしょう。
しかし、証言の後半部分、「竹越か山路であらう」という箇所は、「あらう」という言葉からも明白なように、蘇峰の推測による判断です。「労働者の声」の筆者を特定しているわけではなく、断定もしていません。竹越三叉か山路愛山の執筆であろうと、その蓋然性を述べているに過ぎません。このとき蘇峰は、「労働者の声」の「劈頭の部分を熟視して」はいますが、他に日記やメモを参照した様子はありません。つまり、89歳の徳富蘇峰が、27歳の時に編集刊行した『国民之友』に掲載した一論文の筆者について、記憶だけを頼りに答えたものです。蘇峰は、『国民之友』の論説記者のうち、こうした分野について書き得た人物は竹越三叉か山路愛山しかいなかったと考え、このように答えたものでしょう。おそらくこの時、蘇峰が、社外執筆者の存在に思い及ぶことは、なかったと思われます。なぜなら、家永三郎氏の質問は、「〈労働者の声〉が蘇峰の執筆か、他の同人の筆か、後者ならば誰の筆に成るものか」だったからです。この問いについては、前掲の「『国民之友』研究の思い出」に記されています。要するに、質問者も回答者も、最初から社外執筆者の存在を考慮していないのです。いずれにせよ、家永三郎氏の問いに対する蘇峰の回答が、さらなる検討を要するものであることは明白です。
---------------(引用おわり)
ここで二村氏が提起する論点は二つある。一つは、蘇峰証言における「竹越か山路であらう」という部分は、蘇峰の推測による蓋然性を述べているに過ぎないということ。もう一つは、家永氏と蘇峰との問答は、最初から社外執筆者の存在を考慮していないもので、この点は再検討を要するということ。
第一の論点からみよう。蘇峰証言が「労働者の声」の筆者を断定するものではなく、「蓋然性を述べている」ということについては、私もそのように考えており、異存はない。ただし、ここで蘇峰が、ともかく竹越と山路という二人の名前を明言した事実は、『国民之友』の社説欄がいかなるものだったかを考えるうえで、重要な示唆を与えている(後述)。
第二の論点に移ろう。家永氏と蘇峰との問答は、「労働者の声」の執筆者として「社外執筆者」が存在する可能性を念頭に置いていないことにそもそも問題がある、ということを二村氏は言いたいらしい。つまり二村氏は、家永氏も蘇峰も全然考えてもみなかった「社外執筆者」なるものが存在する可能性を主張している。だが二村氏の議論は、民友社(『国民之友』の発行主体)と何の関係もない高野房太郎が『国民之友』の社説を執筆したなどという、ありそうにもないことの可能性を残しておきたいためにする、無理筋の主張にすぎない。
「労働者の声」は、『国民之友』の「国民之友」欄に掲載された論説である。家永氏はこの「国民之友」欄について次のように説明している。「無署名であって、民友社の主義主張を発表する場所であり、蘇峰の政治的抱負を吐露するための欄である。従って大部分は蘇峰の執筆にかかると思われるが、なかには他の社員が執筆した文もあった」(「『国民之友』」『文学』23号、1955年1月)。また『国史大辞典』には北根豊氏による次の説明がある。「「国民之友」欄は社説欄に該当するところで、無署名であるが民友社すなわち蘇峰の主義主張を掲げた」(『国史大辞典』第五巻〔吉川弘文館、1985年〕)。
「国民之友」欄に掲載された論説は『国民之友』の社説であり、蘇峰ないし蘇峰に代わる民友社員の記者が無署名で執筆し、民友社の主義主張を掲げたものである、という見解は、現在に至るまで、『国民之友』を史料として研究する者の共通認識であろう。例えば、民友社研究で著名な西田毅氏がその著書『竹越与三郎』〔ミネルヴァ書房、2015年〕で、「民友記者として重用された三叉は、蘇峰とともに『国民之友』と『国民新聞』の社説を書いたが、のちに人見一太郎も三叉が書く社説の一部を執筆するようになった。『国民之友』の方は山路愛山も書くようになったという」(64頁)と記しているのも、同様の認識によるものだろう。
「労働者の声」が掲載された『国民之友』95号(1890年9月23日)の原本の縮刷版を確認すると、本号の「国民之友」欄に掲載された社説は「主動者の責任」(1~6頁)と「労働者の声」(6~11頁)の二編であり、ともに民友社の主義主張を掲げる社説としてふさわしい堂々たる内容と分量を備えている。
「労働者の声」をめぐる家永氏との問答で、蘇峰が「これは自分が筆を取つて書いたのではない、竹越か山路であらう、とはつきり答へた」のは、単に漠然と「蓋然性を述べている」にとどまらない。『国民之友』の社説の執筆者は、蘇峰か、蘇峰でなければ竹越・山路といった民友社員の主要な論説記者に限られていたという事実を、当事者たる蘇峰が示唆したものとみるべきではないだろうか。(ただし、山路の民友社入社は1892年であり、1890年の段階では『国民新聞』の寄稿者に過ぎなかった。社説の執筆者としては、他の民友社員の可能性も考える必要があるかもしれない。)
『国民之友』社説の位置づけをめぐって当事者や研究者の間で長年共有されてきた事実認識を、二村氏があえて疑い、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)などという主張を維持したいのであれば、まず『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を挙げることが、最低限必要だろう。さもなければ、「労働者の声」の筆者=高野房太郎説は、二村氏の願望の表現にすぎないといわねばならない。
【2.「労働者の声」竹越三叉執筆説をめぐって】
二村氏は、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と断定的に述べている。その根拠を二村氏は二つ挙げている。一つは「文体の違い」であり、もう一つは「文章の内容」である。
2.1 「文体」をめぐる問題
まず「文体の違い」について、二村氏の述べているところを検討しよう。
二村氏は、竹越の文章を山路愛山が「荘重典麗」と評したことを引きつつ、「竹越三叉の文章は、独特の形容を駆使し、多様な語彙を用いて、特有のリズム感をもっている」と述べる。そのうえで、名文家・美文家として知られた竹越の「荘重典麗」な文体の実例として、『新日本史(中巻)』(1892年)、「近日の文学」(『国民新聞』1890年5月16日〔二村氏が1893年としているのは書き間違いであろう〕)の一部を引き、また比較的説明的な文章の例として『人民読本』(1901年)を引いて、「「抑揚の妙を極めた散文詩」とか「荘重典麗」と言うには程遠い、理詰めの文章」である「労働者の声」とは文体が異なっていると、二村氏は主張している。
だが、二村氏のこうした比較の仕方に説得力はない。竹越が能文家であることは有名だが、そもそも能文家とは、単に〈荘重典麗〉な美文を書くだけでなく、文章の目的やそれを掲載する媒体に合わせてさまざまな種類の文体を駆使する能力をもっている。竹越の膨大な論説の中から都合のよいものを恣意的に引っ張ってきて、それを「労働者の声」の文体と表面的に比較し、文体が異なることをもって、「竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」ことを主張する根拠になるなどと、二村氏は本気で考えているのだろうか?
竹越は「労働者の声」が書かれたのと同じ1890年の初めに民友社に入社し、とりわけ『国民新聞』社説ならびに論説記事を担当する記者として活躍した(西田、前掲書)。そもそも『国民新聞』は、当時の新聞界が知識人向けの政論新聞である「大新聞」と庶民向けの娯楽的な「小新聞」とに棲み分けられていた状況で、多面性と平易性を併せ持つ「中新聞」として蘇峰が企画し創刊したものであった(有山輝雄『徳富蘇峰と国民新聞』〔吉川弘文館、1992年〕10~15頁)。そのような「中新聞」を中心的に担う論説記者として、竹越は多くの無署名記事を執筆したのである。
私も二村氏にならって、竹越の執筆した『国民新聞』論説の中から恣意的に選び出してみよう。以下に引用するのは、「下層社会の智見を啓発するの一手段」(『国民新聞』1891年6月29日)(『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』〔三一書房、1985年〕所収)という記事である。
「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか、是れ第一の社会問題也。如何にして下層社会の智見を開発すべきか、是れ第二の社会問題也。第一問題を講ずるものは必らず第二問題に及ぼさざるべからず。吾人は此に下層社会の智見を啓発するの一案として、手軽るき書籍館を開かんことを望む。現今上野に政府の図書館あり、神田に私立の書籍館ありと雖も、是等は多くは学者の考証、若しくは銭なき書生を目当とする者にして、其蔵する所の書籍も多くは此目的に適したる者也。且つ其学問を目当として遊楽を目当とせざるや、朝の八九時に初りて夕の五時に終る、夕の五時は正さに是れ下層社会にある者が、営々として道途に汗絞るの時也。到底今日の書籍館を以て、下層社会を啓発するの用に供するに足らざる也。書生学者は自ら求めても智識を研くべし。種々なる便宜を与へて之を誘ふは、下層社会に於てこそ要ある也。吾人は神田、芝、日本橋若しくは地方の小都会に於て、社会改良に志ある者が一個の手軽き書籍館を設け朝より開館して夕の九時までも開き、普通学の一斑、卑賤より立身したる大人物の伝記、歴史の一斑、世界事情旅行記、清潔なる小説、新体詩、等を集めて丁稚、小僧、労働者等の智見を開発するに便ならしめんことを望む。」
上の記事の文体と、二村氏が引用した同じ『国民新聞』での竹越の記事「近日の文学」の〈荘重典麗〉な文体とを比較すれば、竹越が多様な文体を状況に合わせて駆使できる能文家であったことが理解できるだろう。なお、上の記事にある「如何にして富を下層の社会にも分配して貧富の喧騒を防ぐべきか」という「第一の社会問題」についての竹越の言及は、内容的に「労働者の声」に通じるものとして注目すべきだろう。
2.2 「文章の内容」をめぐる問題
次に、竹越の著作と「労働者の声」とは「文章の内容」において異なる、という二村氏の主張を検討しよう。
二村氏は次のように述べている。
----------------(引用はじめ)
周知のように竹越与三郎は『新日本史』、『二千五百年史』、『日本経済史』など大部の通史・史論を刊行し、また『国民之友』をはじめ『六合雑誌』『国民新聞』『世界之日本』など数多くの雑誌・新聞に、多数の論稿を執筆しています。しかし、これらの著書や論稿のどこを探しても、「労働者の声」の筆者であれば、当然、論ずるであろう、労働問題に関する言及がないのです。
----------------(引用おわり)
二村氏は「これらの著書や論稿のどこを探しても…(中略)…労働問題に関する言及がない」と断言しているが、それは正しくない。
例えば、「経済書と聖書」(『六合雑誌』110号、1890年2月15日)という竹越の文章を次に引用しよう(引用に際し、原文の句読点を改めてある)。
「今日の文明は、実に物質的文明の大に発達せるときなり。凡そ二三十年前の人が夢にも幻にも知らざりし事多く今日に行はれ、取り分け生産力、即ち物を作り出す力大に発達せり、例せば紡績器、若しくは活版器械は、蒸気器の如し、此等は器械が一振するや、数百千の工夫が汗水垂らして働くよりも、多量なる物品を製出す。…(中略)…其富なるものは、僅に少数の人々の手に入りて、其他の多数は、以前として貧しく、富と云ふ太陽は背の高き大金持の頭を照らすも、背の低き、小商人、小農夫、労働者の頭を照らすことなし。…(中略)…見よ、鉄道は長く日本を貫ぬく、然れども鉄道のために、無数の民は其職業を失す。見よ、製造会社は立つ、之がために無数の細民は其業を擲つ。…(中略)…今日の文明は、僅かに其富の製産のみを実行して、社会の富を、地主に、金利に、労働者の賃金に、農夫の所得に、分配を適宜にするの方を講ぜず。」
上の文章は「労働者の声」の七か月前のものだが、社会問題に対する竹越の関心のなかに、生産の機械化・巨大化に伴う失業の深刻化や、労資間の分配の不公平など、労働問題への視点の萌芽が表れていることは、ある程度見て取ることができる。
また、「国家社会主義」(『世界之日本』第2巻第2号、1898年9月17日)(前掲『民友社思想文学叢書第4巻 竹越三叉集』所収)で、竹越は次のように述べている。
「第三級民は、決して生活の自由を有せず。彼等は其労力に相当なる賃金を受る能はず。彼等は安楽に其家族を養ふ能はず。…(中略)…殊に製造所の持主と職工との関係に至りては最も甚し。製造所の持主は、固より資本家なるが故に、其利益によりて更らに其事業を拡張し、其利益を増進するの道あるに引きかへて、職工は日々の所得によりて衣食し、衣食に費したる残余は幾何もあらず。而して時として疾病あり、時として災難あり、遂に一年を平均して何の貯蓄する所なきに至る。夫れ製造所の主人の資本が富なるが如く、職工の労力のまた一種の富也。然るに一方は其富を倍加しつゝ行く間に、一方は依然として其富を加ふる能はざるのみならず、遂に其労働の結果として、衰病を得て死し、家に一物を止めず、妻子離散、或は人の門によりて食を乞ひ、甚しきは転じて売淫窟に堕落するに至りては、豈に傷心の極ならずや。我輩は多くの職工の境遇は其血肉を売つゝ資本家の事業を経営する者なりと云ふの適当なるを見る。」
上の論説には、明白に「労働問題に関する言及」をみることができる。労働問題への関心は、強弱の差こそあれ、少なくとも1890年代の竹越の論説の中にしばしばみられるのである。
『国民之友』には、「労働者の声」以後も、労働問題を論じた社説がしばしば現れる。例えば、「平民主義第二着の勝利」(139号、1891年12月13日)、「社会立法の時代」(157号、1892年6月13日)、「社会問題の新潮」(169号、1892年10月13日)などである。これらの社説は、労働組合・八時間労働制・職工条例・ストライキなど、労働問題を具体的に論じたものである。また『国民新聞』にも、「政治上に於ける社会主義」(1892年7月27日)、「聯合追放」(1892年10月28日)、「労働問題」(1892年12月8日)、「工場の立法」(1892年12月25日)など、労働問題をテーマとする社説は少なくない(佐々木敏二「『国民之友』における社会問題論」『キリスト教社会問題研究』(18号、1971年3月)を参照)。これら『国民之友』『国民新聞』の社説はいずれも無署名であるが、社説を執筆する可能性のある民友社記者のなかでも、竹越は社会問題・労働問題に早くから関心を抱いていた以上、彼がこれらの社説にも関わっている可能性については今後検討する余地がある。
2.3 小括
以上検討してきたように、「三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近い」と二村氏が主張する二つの根拠(竹越の文章と「労働者の声」との文体の違い、および両者の内容の違い)は、いずれも説得力を欠いている。したがって、二村氏の主張は客観的に支持され得ないものと結論できる。
【3.「労働者の声」高野房太郎執筆説が成り立ち得ない理由の追加】
【1】で述べたように、二村氏の「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」(二村、前掲書、102頁)という主張が、そもそも歴史学的に検討の余地のある仮説として成り立つには、『国民之友』社説を「社外執筆者」が書いたことの明らかな実例、それも当時の高野のように民友社とはおよそ無縁で同誌に寄稿したことすらない無名の若者が同誌の社説を執筆したという実例を、二村氏自身が明示することが最低限必要である。だが二村氏はそれを全く明示できていない。
また、二村氏が「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という主張の根拠として挙げている四点が、いずれも根拠として薄弱であることについては、すでに拙著で説明したとおりである(本ブログ記事を参照)。
以上の理由だけでも、「「労働者の声」の筆者は高野房太郎に違いない」という二村氏の主張がもはや存立の余地のないことは明白だろう。
さらにここでは、「労働者の声」の文章の内容からみても、高野房太郎が筆者であるとは考えがたい理由を、一つ付け加えておきたい。
「労働者の声」の一節を下に引用する。
「米国の如きも、ナイト、オフ、レバー(労働的の武士)なる者あり。其初や一種の秘密結社にして、其党員は皆暗語を有し、その徽号を有し、隠然たる運動を為せり。而して其勢力漸次に増加し、五年前に於ては、既に二百万人の会員を有するに至れり。亦盛なりと云ふべし。」
ここで言及されている「ナイト、オフ、レバー」とは、1869年にフィラデルフィアで創立された労働団体の労働騎士団(Knights of Labor)のことである。二村氏は『明治日本労働通信』(岩波書店、1997年)の注のなかで、労働騎士団は1886年に最盛期に達したものの、同年のヘイマーケット事件やアメリカ労働総同盟(American Federation of Labor, AFL)の結成によって打撃を受け、急速に衰退していった旨を記している。
「労働者の声」における労働騎士団への言及は、「五年前」すなわち同団体の衰退前の情報を用いていることが明らかである。
一方、1890年当時アメリカに滞在中で、当地の労働運動を注視していた高野は、それよりもはるかに新しい情報に接する立場にあった。事実、高野がワシントン州タコマから1890年4月に『読売新聞』に寄稿した論説「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」(同年5月31から6月27日にかけて連載)には、アメリカ労働運動の最新の情報を次のように記している。
「今や米合衆国中において最も有力なる二個の会合、すなわち五十九万余人を率いるアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアー及び三十余万の会員を有するナイト・オフ・レーボアーは、本年五月一日を期し互いに連合して八時間労働請求の運動を為さんとす」(前掲『明治日本労働通信』所収、275頁)。
高野はAFLが最有力の労働団体として五十九万余人を擁し、労働騎士団はそれに次ぐ三十余万に過ぎないことを書いており、1890年5月1日の記念すべき第一回メーデーの予定まで熟知していた。彼は、「千八百八十六年十二月合衆国中における五十九個の労役者の会合が合してアメリカン・フェデレーション・オフ・レーボアーを形造」(同上書、276頁)ったことを、労働組合運動の強化の方向として重視していたのである。
二村氏によれば高野が「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」を日本に向けて投函したのは4月30日である(二村、前掲『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』93頁)。仮に高野が「労働者の声」の筆者だとすると、「労働者の声」の執筆は「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」の投函から少し後のはずである。とすれば、なぜ「労働者の声」ではわざわざ五年前の古い情報に基づいて労働騎士団だけを紹介し、AFLについては全く言及しないのだろうか?なぜ第一回メーデーなどの最新の情報を伝えないのだろうか?全く不可解というほかない。このことも、「労働者の声」を高野が執筆した可能性が否定されるべき理由の一つである。
私は、高野の「北米合衆国の労役社会の有様を叙す」や、「日本に於ける労働問題」(『読売新聞』1891年8月7~10日)は、アメリカで労働組合運動に接し、労働問題について深く考察した高野でなければ書くことのできない稀有の論説だと思う。だが「労働者の声」は、高野でなくとも、日本で欧米の労働問題に関心を持ち、欧米から流れてくる書籍や新聞の情報に接する立場にある者なら、書くことができる内容であると考える。
追記:
私は中国在住のため、このブログ記事を書くにあたり、手持ちの乏しい史料と研究書・論文、および国会図書館デジタルコレクションでオンライン公開されている史料を用いるにとどまり、今回参照したくてもできなかった研究や史料が少なくない。したがって、「労働者の声」の筆者を確定するにはまだ程遠い状態にある。竹越あるいは他の民友社員の可能性を含め、「労働者の声」の筆者をめぐるさらなる追究は今後の課題としたい。
追記2:
文章の一部を補訂しました(2018年5月14日・5月15日)
追記3:
ここでの拙論に対する反論として、二村氏は2018年5月20日、WEB版『二村一夫著作集』に「大田英昭氏に答える─〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(3)」を掲載しました。それに対する私からの再批判として、本ブログに下の一連の論稿をアップしたので、ご参照ください(2018年6月18日)
①再び二村一夫氏の反論に答える(1)
②再び二村一夫氏の反論に答える(2)
③再び二村一夫氏の反論に答える(3・完)
2018-05-13 20:05