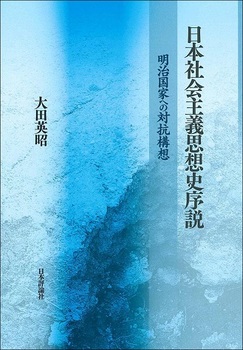書評:鄭玹汀『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』 [日本・近代史]
鄭玹汀著『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館、2013年2月)に対する私の書評が、『初期社会主義研究』(25号、2014年5月)に掲載されました。下に転載します。
----------------------------------------
ここ数年来、日本社会のあちこちでナショナリズムの狂熱が噴出している。かつてインターネットの世界に閉じ込められていた民族差別な言辞が、突然現実の街路に飛び出し、日の丸や旭日旗を振り回す排外主義団体のデモの怒号となって東京の白昼の路上でもしばしば耳にするようになった。ここは本当に二十一世紀の日本なのか、と目を疑いたくなるような光景である。昨年(二〇一二年)末の安倍晋三政権の発足以来、排外的国家主義の圧力が公共の場の言論に対しても強まっているのは確かだ。領土問題でやや踏み込んだ発言を行った元首相に対しては、現職の閣僚から「国賊」という言葉が投げつけられた。あたかも時計の針が「戦前」へと逆戻りしたかのようである。
日本社会全体に強まりつつある国家主義の圧力は、権力を批判する側の人びとの立ち位置すら微妙に変化させているようにみえる。例えば反原発・反TPPを掲げる運動や言論においても、普遍的な人権を根拠として立論するよりもむしろ、「国民国家」を守るためといったナショナルな立場からの主張が目立ってきている。「反日」「左翼」というレッテルを張られることを恐れる空気が強まるなかで、「保守」「愛国者」を自称する論客が若い世代に増えている。日本近代思想史研究の分野で近年、保守思想に関心が集まっていることも、そうした空気の反映なのかもしれない。
日本社会の右傾化が目立つ中、二〇一三年二月に刊行された鄭玹汀氏の『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館)は、反時代的であるがゆえにタイムリーな意義をもっている。本書の主人公である木下尚江は、私見によれば、近代日本においてナショナリズムと国体論に対する最もラディカルな批判を敢行した思想家の一人である。本書は、清水靖久氏の『野生の信徒 木下尚江』(九州大学出版会、二〇〇二年)以来約十年ぶりに現れた木下に関する本格的な研究書であり、木下の真骨頂である国家主義批判の思想と正面から取り組みつつ、彼を中心に明治キリスト教界のあり方全体を視野に収めた労作といえる。
本書が研究対象とする時代は、一八八〇年代後半から一九一〇年頃に至る二十数年間である。大日本帝国憲法および教育勅語の発布から日清・日露の両戦争を経て大逆事件に至るこの時期、明治政府は天皇制イデオロギーによる急速な国民統合の実現を目指していた。そうした動きに、キリスト教界がどのように対峙ないし屈服していったかを考察することに、本書の主眼が置かれている。植村正久・海老名弾正・巌本善治ら明治キリスト教界を代表する指導者たちは、キリスト教への圧迫が強まるこの時期、天皇制イデオローグの呼号する国家主義や家族主義への妥協を重ねていった。他方で木下ら少数のキリスト者たちは、そうした教界主流の姿勢を厳しく批判したのである。従来注目されてこなかったこの両者の思想的対決を、鄭氏はスリリングな筆致でえぐりだしている。
本書の議論で最も興味深く思われるのは、「武士道」思想をめぐる両者の対立である。植村正久ら明治期の代表的キリスト者の多くが武士道を称揚したのは周知のことだが、従来の研究はこれをキリスト教の土着化として積極的に捉えるものがほとんどであった。そうした先行研究に対し、鄭氏は異を唱える。植村らによる武士道の宣揚は、キリスト教を反国家的だとするナショナリスト勢力の攻撃から身をかわし、キリスト教が愛国や国粋保存と調和することを示すためという側面があった。日清・日露戦争にキリスト教界が積極的に加担する論理としても武士道は用いられた。木下の武士道批判はキリスト教界主流のこうした姿勢を指弾するもので、日露戦争を是認するか否かをめぐって両者の対立は頂点に達することが、本書で詳しく論じられている。世界に誇る日本の伝統的な倫理思想として武士道をもてはやす声が近年とみに高まっているが、そうした風潮の危うさに警鐘を鳴らすものとして、木下の武士道批判が掘り起こされたことの意義は小さくない。
さらに、明治キリスト教界の女性論をめぐる本書の研究も、たいへん刺激的である。教界主流の女性論の保守化、内村鑑三ら男性中心主義的なキリスト者と日本基督教婦人矯風会との対立、矯風会内部の保守派と進歩派との対立など、時代の変遷とともに変化する複雑な構図が丁寧に解きほぐされている。そして女性の社会的役割をめぐるこうした教界内の論争が、天皇制イデオロギーの支柱の一つである家族主義の受容についての葛藤を反映していたこと、したがってそこには天皇制国家体制へのキリスト教界の統合という問題も蔵されていたことが、解明されている。鄭氏によれば、当時もっとも進歩的でラディカルな女性観をもっていたキリスト者の一人が木下であった。彼は廃娼運動を通じて矯風会の進歩派の女性クリスチャンと交流を深め、最も弱い立場に置かれた娼妓を主体とする人権運動の構想へと、女性解放の思想を深めていった。木下が婦人参政権をいち早く主張し、その獲得のための運動を矯風会の女性たちに呼びかけていた事実を、鄭氏が新資料の発掘によって明らかにしたことは、日本政治思想史研究のうえでも貴重な成果といえよう。
木下尚江研究の重要なテーマの一つとして、一九〇六年秋以降の彼における思想上の変化をどのように捉えるか、という問題がある。従来の研究では、木下は母親の死などをきっかけに政治運動・社会運動から撤退し、キリスト教信仰にも動揺をきたして修養運動に参加するなど、急速に内面化してゆく、という理解が一般的といえよう。だが鄭氏はこうした見方にも疑問を呈している。すなわち木下の思想変化の基本線は、従来の都市知識人中心の運動を農村民衆中心の運動へと止揚することを目指す、という運動観の転回にあり、谷中村残留民との関わりの中にこの方向が示唆されているという。それと並行して、女性観においては都市の中・上流婦人からなる矯風会に対する木下の期待が失われた一方、農山村の最底辺の女性たちに変革への希望が託されるようになった。その間、彼の国家権力批判はますます熾烈となり、その背景として彼のキリスト教信仰における「神の国」観が深化したことが指摘されている。木下の思想変化の本質をめぐる本書のこうした叙述はまだスケッチにとどまっているが、従来の研究を刷新すべき重要な指摘が含まれていると思う。今後さらにこの問題をめぐる考察が深まることを期待したい。
本書を通読して見えてくることは、廃娼運動・社会主義運動・反戦運動など、木下の参加したあらゆる運動における彼の主張の根底に、天皇制批判の思想が脈々と流れていることである。明治日本の思想家のなかで、天皇制・国体論批判の深度において木下の右に出る者はいないだろう。近代日本の社会・政治運動において、天皇制問題が現在に至るまでしばしば躓きの石となってきたことを振り返るとき、彼の天皇制批判は燦然と光を放っている。天皇元首化に向けた憲法改正を右派支配層が推し進めようとしている現在、権力を監視し批判する側の人びとの間ですら、天皇制を儀礼的な君主制の一形態として肯定、むしろ賛美する言説がじわじわと広がっている。近代日本のキリスト教界は天皇制イデオロギーといったん妥協して以後、帝国日本の侵略戦争に協力する方向へずるずると引き込まれていった。それは決してキリスト教界だけの問題ではないし、また過去の問題でもない。東アジアにさまざまな不幸をもたらした日本ナショナリズムにおいて、天皇制はいかなる役割を果たしてきたのか、また現に果たしつつあるのか。私たちはそのことをもう一度熟考する必要があるし、今日木下尚江を読み直す最大の意義もそこにある。そのために本書は最も適切な案内役となるだろう。

----------------------------------------
ここ数年来、日本社会のあちこちでナショナリズムの狂熱が噴出している。かつてインターネットの世界に閉じ込められていた民族差別な言辞が、突然現実の街路に飛び出し、日の丸や旭日旗を振り回す排外主義団体のデモの怒号となって東京の白昼の路上でもしばしば耳にするようになった。ここは本当に二十一世紀の日本なのか、と目を疑いたくなるような光景である。昨年(二〇一二年)末の安倍晋三政権の発足以来、排外的国家主義の圧力が公共の場の言論に対しても強まっているのは確かだ。領土問題でやや踏み込んだ発言を行った元首相に対しては、現職の閣僚から「国賊」という言葉が投げつけられた。あたかも時計の針が「戦前」へと逆戻りしたかのようである。
日本社会全体に強まりつつある国家主義の圧力は、権力を批判する側の人びとの立ち位置すら微妙に変化させているようにみえる。例えば反原発・反TPPを掲げる運動や言論においても、普遍的な人権を根拠として立論するよりもむしろ、「国民国家」を守るためといったナショナルな立場からの主張が目立ってきている。「反日」「左翼」というレッテルを張られることを恐れる空気が強まるなかで、「保守」「愛国者」を自称する論客が若い世代に増えている。日本近代思想史研究の分野で近年、保守思想に関心が集まっていることも、そうした空気の反映なのかもしれない。
日本社会の右傾化が目立つ中、二〇一三年二月に刊行された鄭玹汀氏の『天皇制国家と女性――日本キリスト教史における木下尚江』(教文館)は、反時代的であるがゆえにタイムリーな意義をもっている。本書の主人公である木下尚江は、私見によれば、近代日本においてナショナリズムと国体論に対する最もラディカルな批判を敢行した思想家の一人である。本書は、清水靖久氏の『野生の信徒 木下尚江』(九州大学出版会、二〇〇二年)以来約十年ぶりに現れた木下に関する本格的な研究書であり、木下の真骨頂である国家主義批判の思想と正面から取り組みつつ、彼を中心に明治キリスト教界のあり方全体を視野に収めた労作といえる。
本書が研究対象とする時代は、一八八〇年代後半から一九一〇年頃に至る二十数年間である。大日本帝国憲法および教育勅語の発布から日清・日露の両戦争を経て大逆事件に至るこの時期、明治政府は天皇制イデオロギーによる急速な国民統合の実現を目指していた。そうした動きに、キリスト教界がどのように対峙ないし屈服していったかを考察することに、本書の主眼が置かれている。植村正久・海老名弾正・巌本善治ら明治キリスト教界を代表する指導者たちは、キリスト教への圧迫が強まるこの時期、天皇制イデオローグの呼号する国家主義や家族主義への妥協を重ねていった。他方で木下ら少数のキリスト者たちは、そうした教界主流の姿勢を厳しく批判したのである。従来注目されてこなかったこの両者の思想的対決を、鄭氏はスリリングな筆致でえぐりだしている。
本書の議論で最も興味深く思われるのは、「武士道」思想をめぐる両者の対立である。植村正久ら明治期の代表的キリスト者の多くが武士道を称揚したのは周知のことだが、従来の研究はこれをキリスト教の土着化として積極的に捉えるものがほとんどであった。そうした先行研究に対し、鄭氏は異を唱える。植村らによる武士道の宣揚は、キリスト教を反国家的だとするナショナリスト勢力の攻撃から身をかわし、キリスト教が愛国や国粋保存と調和することを示すためという側面があった。日清・日露戦争にキリスト教界が積極的に加担する論理としても武士道は用いられた。木下の武士道批判はキリスト教界主流のこうした姿勢を指弾するもので、日露戦争を是認するか否かをめぐって両者の対立は頂点に達することが、本書で詳しく論じられている。世界に誇る日本の伝統的な倫理思想として武士道をもてはやす声が近年とみに高まっているが、そうした風潮の危うさに警鐘を鳴らすものとして、木下の武士道批判が掘り起こされたことの意義は小さくない。
さらに、明治キリスト教界の女性論をめぐる本書の研究も、たいへん刺激的である。教界主流の女性論の保守化、内村鑑三ら男性中心主義的なキリスト者と日本基督教婦人矯風会との対立、矯風会内部の保守派と進歩派との対立など、時代の変遷とともに変化する複雑な構図が丁寧に解きほぐされている。そして女性の社会的役割をめぐるこうした教界内の論争が、天皇制イデオロギーの支柱の一つである家族主義の受容についての葛藤を反映していたこと、したがってそこには天皇制国家体制へのキリスト教界の統合という問題も蔵されていたことが、解明されている。鄭氏によれば、当時もっとも進歩的でラディカルな女性観をもっていたキリスト者の一人が木下であった。彼は廃娼運動を通じて矯風会の進歩派の女性クリスチャンと交流を深め、最も弱い立場に置かれた娼妓を主体とする人権運動の構想へと、女性解放の思想を深めていった。木下が婦人参政権をいち早く主張し、その獲得のための運動を矯風会の女性たちに呼びかけていた事実を、鄭氏が新資料の発掘によって明らかにしたことは、日本政治思想史研究のうえでも貴重な成果といえよう。
木下尚江研究の重要なテーマの一つとして、一九〇六年秋以降の彼における思想上の変化をどのように捉えるか、という問題がある。従来の研究では、木下は母親の死などをきっかけに政治運動・社会運動から撤退し、キリスト教信仰にも動揺をきたして修養運動に参加するなど、急速に内面化してゆく、という理解が一般的といえよう。だが鄭氏はこうした見方にも疑問を呈している。すなわち木下の思想変化の基本線は、従来の都市知識人中心の運動を農村民衆中心の運動へと止揚することを目指す、という運動観の転回にあり、谷中村残留民との関わりの中にこの方向が示唆されているという。それと並行して、女性観においては都市の中・上流婦人からなる矯風会に対する木下の期待が失われた一方、農山村の最底辺の女性たちに変革への希望が託されるようになった。その間、彼の国家権力批判はますます熾烈となり、その背景として彼のキリスト教信仰における「神の国」観が深化したことが指摘されている。木下の思想変化の本質をめぐる本書のこうした叙述はまだスケッチにとどまっているが、従来の研究を刷新すべき重要な指摘が含まれていると思う。今後さらにこの問題をめぐる考察が深まることを期待したい。
本書を通読して見えてくることは、廃娼運動・社会主義運動・反戦運動など、木下の参加したあらゆる運動における彼の主張の根底に、天皇制批判の思想が脈々と流れていることである。明治日本の思想家のなかで、天皇制・国体論批判の深度において木下の右に出る者はいないだろう。近代日本の社会・政治運動において、天皇制問題が現在に至るまでしばしば躓きの石となってきたことを振り返るとき、彼の天皇制批判は燦然と光を放っている。天皇元首化に向けた憲法改正を右派支配層が推し進めようとしている現在、権力を監視し批判する側の人びとの間ですら、天皇制を儀礼的な君主制の一形態として肯定、むしろ賛美する言説がじわじわと広がっている。近代日本のキリスト教界は天皇制イデオロギーといったん妥協して以後、帝国日本の侵略戦争に協力する方向へずるずると引き込まれていった。それは決してキリスト教界だけの問題ではないし、また過去の問題でもない。東アジアにさまざまな不幸をもたらした日本ナショナリズムにおいて、天皇制はいかなる役割を果たしてきたのか、また現に果たしつつあるのか。私たちはそのことをもう一度熟考する必要があるし、今日木下尚江を読み直す最大の意義もそこにある。そのために本書は最も適切な案内役となるだろう。

2014-06-07 17:41